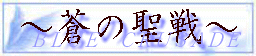
第一章 〜時の発端〜
【1】
共にあって欠けないもの 空に光が駆る時 月の魔法が動き出す カランッ……と透明なカットグラスの中に小さな音が響く。 僅かに残った焦茶色の液体が、涼しげな音に拍車をかけてやや暑さを残した室内に広がる。 その中身を空にし、無造作に水滴のついたグラスを手にした褐色の腕が延びて カウンターへと差し伸べられる。 「……マスター。アイスコーヒーシロップ付きでお代わり」 「……またかい? 何を待ってるんだか……」 「まぁ恋人じゃないのは確かだよ。それにこういう時はウォッカと相場が決まってるが、生憎俺は酒が嫌いでね」 おおよその見当で誰にでも20歳前後に見えるだろう、ごく普通の青年。 取り立て目立つものがあるわけでもなく、探せばどこにでもいそうな容貌だった。優しげでもなく、厳しそうでも無く。かといってかっこいいわけでも、不細工なわけでもない。 一時的に客の減る昼過ぎに、アイスコーヒーだけを手にノイズだけのラジオを聞いている のがなんとも奇妙だった。 だが、それ以外はどこからどう見ても普通すぎる青年だ。 あえて言えば、そんな普通な所が不可解な――不思議な雰囲気を醸し出しているかも しれない。 ふと、喫茶店のマスターはそんな不思議な青年に興味を引かれた。 「さっきから一体何を聞いてるんだ? 俺にはノイズしか聞こえないんだが」 「……ん、あぁ、これか。ただのノイズだよ。俺は昔からこれが好きでね」 「ただの雑音が?」 「ああ……波の音を聞いているみたいでな。何故だか安心するんだ」 「……変なもんが好きなんだね、お客さん」 「そうかぁ? よくいるぜ?」 知り合いにも結構いるしな、と零れる笑みをそっと噛締めるような表情で呟くのが、この青年にはよく似合っていた。 店の入り口に、微かに幼い子供や若者たちの楽しげな笑い声が響いてゆく。 喫茶店のマスターが視線を向けると、制服姿の学生たちやランドセルを持った小学生が楽しそうに道を歩いていく所だった。それに混じり、買い物をする主婦がいる。 「もうこんな時間か……さてお客さん。何回目か忘れたが、お代わりいるかい?」 「お、気がきくねぇ♪ そうだな……次はアイスティー頼むよ」 「あいよ」 「さて……」 彼は小さく呟くと、カウンターに置いてあった小型のラジオを手に取った。 「そろそろチャンネルかえるか……ん? なんだ、こりゃ?」 ラジオから響く歌に、彼は静かに耳を澄ます。若いというよりも幼いといった方がしっくりする少女のア・カペラ。 どこか、ふざけたような、からかいとやっかみを含んだ、そんな不思議な歌詞が途切れ途切れに聞こえてくる。 <……ザザッ……青い……ザッ……太陽……> それらの意味不明な抽象的な言葉の羅列に、どこか祈るような雰囲気が込められているのに気付くものはいるのだろうか。そして、それに隠された切なる想いにも。 「月の……魔法? 動く……聞いた事ない歌だな……」 奇妙な、不安のような感情に苛まれながらも、それはどこか強く引き込まれる雰囲気を持っていた。ゆっくりと、それを聞かずにはいられない。 彼は、次第にこの不思議な歌に引き込まれていった。 歪んだダンスを踊りましょう 明るく光る宝石と 冷たく光る剣を持ち 先へと向かって走り出す 幼い少女の流麗な歌声に、若い女性の稚拙な歌声が混ざりだす。決して混じり合いそうにもない対照的な二つの歌声は、天上の奇跡のように複雑に絡み合い、同化していく。 <……でも 忘れてはいけないよ あなたに潜む感情を……> 切ない悲しみと共に淡い期待を込めたかのような声が、声の主たちの感情を何よりも強く、はっきりと表している。だが、それに気付いたものはいない――いるはずがない。それは、全ての『真実』を歌った歌ではないから。『真実』は未だ、そして長い時を深い霧の中、終着の無い深淵に埋もれているのだから。 全ては、ひと欠片の『虚像』、『偽り』から、そして“これから生まれる”のだから。 (忘れては、いけない――) 彼が心のうちで密かに抱いている、自分自身への不安がひっそりと呼び覚まされていく。 自分が普通の人間ではないのだという、違和感。幼い頃から決して消える事の無かったソレは、ゆらめく灯火のように儚いながらも、確かに彼の内の存在していた。そして、それは後の世では間違う事無き真実にとなりえるものだから。 そんな摩訶不思議な歌に引き込まれ、遠い果ての世界へと誘われる、その瞬間。 「はい、お待ち」 「――えっ?」 「えって、だから、アイスティー」 「あ、ああ。どうも」 マスターの不思議そうな顔に、一瞬にして現実感が甦ってきた。体が知らずの内に緊張して、どっと身体中から冷や汗が滲み出てくる。 彼は慌ててグラスを受け取り、とりあえず半分ほどをぐいっと飲干して大きな溜息を落とした。 「……考え事でもしてたのかい? ぼーっとしてたみたいだが」 「まあ、ね。ちょっとしたことだよ」 一息ついて初めて全身に鳥肌がびっしりと立っていることに気がついた。俯けた顔は、恐らく血の気を失っているのではないだろうか。酷く寒い気がする。 (一体なんだったんだ、さっきのは……幻覚、か?) グラスの残りを一気にあおり、飲み干すとさっと立ち上がる。コツンと音が鳴り、置いたグラスの底には混ざりきっていなかったシロップが僅かに残っていた。 隣の椅子にかけておいた薄手のコートと大して中身の入っていなかったナップザックを取り上げ、急いでポケットから財布を取り出す。小さく震える手で紙幣を取り出すと、それをばっとカウンターの上に放り出すようにして置く。 「そ、そろそろおいとまするよ。これ、勘定」 「……はぁ、まいど」 レシートを受け取ると、後ろを振り返ることもせずに店を足早に去っていく。 あそこに、いたくなかった。 小さな小さなラジオから、また歌声が流れてくるのではないかと、そんな恐怖感が青年を急き立てていた。あの歌のどこが恐いのか、何が恐いのか、それすらもわからない。だが、一刻も早くその場所から離れたかった。 それだけで頭が一杯になり、彼はほとんど走るようなスピードで通りを歩いた。 すると、突然目の前に小さな影が現れる。そのまま彼はそれに突撃してしまった。 「――きゃっ!?」 「――うわっ?!」 強い衝撃と共に聞こえた小さな悲鳴が、恐慌状態に陥っていた彼を再び正気に戻した。 「あ、すまない! 大丈夫か!?」 「いったぁ……」 セーラー服を身に纏った少女が、尻餅をつく格好で目の前に座り込んでいた。中学生ほどだろうか、驚きに目を見張っている。 慌てて手を差し伸べると、それを遮って少女は慌てた様子でさっと立ち上がった。 「す、すみません! 前を見てなくて……」 「いや、悪いのは俺の方だ。怪我は?」 「大丈夫です。本当にすみませんでした」 じゃあ、と言うと少女は足早に走っていった。随分とせっかちなようだが、なかなか元気のいい少女だ。はきはきとものを言い、慌てたようすだった。何か、用事でもあったのだろうか。 (あの子と、どこかであったか? いや、気のせいか) 「ダメだな……気をつけないと」 苦笑を漏らし、少女の駆けていった方角にゆっくりとした足取りで歩き始めた。 特に目的のみつからないまま、なんとはなしに進んでいた彼はいつしかさっきの歌を口ずさんでいた。 「――青い月と 赤い太陽 共にあって欠けないもの――」 わずかな時を置いただけなのに、先ほどは不自然なほどに恐れていたあの歌を今ではもう何も感じすに声にしてゆく。恐れるどころか、むしろ心安らぐような暖かな安心感が広まった。 先ほどまで持っていた恐怖などの感情が消え去り、胸には暖かな物が満ちている。 (そういや、なんだったんだろうな……なんか、今日はあの喫茶店に行かなきゃいけないような気がしたし、何かを待ってなきゃいけないような気もしたしなぁ) ぶらぶらとただ気の向くまま、人の少ないほうへと足を進める。自然と、木々の姿が増えて都会の喧騒が遠のいていく。それに伴って鳥などの動物や、幼い子供連れの親子の姿が目に入るようになった。 「お? 中央公園まで歩いてきちまったか」 彼はいつのまにか、広々とした公園にたどり着いていた。この辺りではかなり大きな公園で、遊具などは何も無いが緑豊かで町中の喧騒からもかなり離れているため、いつも人が絶えない。 安らいだ気持ちになっていた彼は、偶然目に入った所にあった空色のベンチにドサッと音を立てて座り込む。腕を投げ出し、だらしない仕草で深く息を吸い込んだ。 「ああ……なんか、疲れたな」 別に何かを意図した訳でもなく、ほんとうにたまたま彼は上を向いた。そしてそれが、これからの彼の運命を大きく変える最初の一歩となった。 彼がなんとはなしに僅かに傾いた太陽を見上げた、その刹那。世界の――この次元の全てで『何か』が変わった。 幼い少女の声にも似た『何か』を脳裏ではっきりと感じた次の瞬間、見上げていた大空に異変が起こった。 その声に疑問を感じる暇も無く、大きく目を見開く。 「な、んだよ、ありゃあ!?」 飛びずさるようにして立ち上がる彼の目線の先には、雲ひとつ無い美しい青い空。 そして――蒼い光を放つ、巨大な彗星。 「――っ」 叫ぶ暇もなく、彼の視界を――世界の全てを、光が包み込む。意識も、存在もすべてが光に飲み込まれていった。 彼の意識が光の洪水に飲み込まれて途切れる寸前、あの不思議な歌が脳裏に甦ってきた。涙がでるほど、懐かしいと――そう思える、そう思った自分がいたことに今更ながら気がついた。 (どうして……あんなに懐かしいと、そう思ったんだろう……) 月の魔法が動き出す 青い光に導かれ 妖精たちが降りてくる 世界中の異なる場所で、たくさんの人が同じものを見た。 先ほど彼とぶつかった少女が、ランニングをしていた少年達が、街で遊んでいた若者達が、親と歩いていた幼い子供が、そして数え切れない人々が。 世界中の異なる時間に、たくさんの人が同じ光を見た。 この日、原因不明の謎の彗星が世界各地で目撃された。 実害のない蒼の光の塊は人々の瞳に焼きつき、次の瞬間には消滅していたという。 そして、それと同時にあっけないほど簡単に、世界は変わってしまった。 |



Copyright(C) 2001- KASIMU all rights reserved.