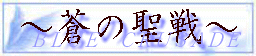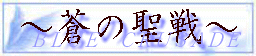――I've walked so long I can't remember-where was my home?
Their distant faces fade away i'm always on my own
I can show smile, it's not hard to do
I can have the strength to go on
But sometimes I wanna let go of everything……
月明かりだけが彼らの悲しみを嘆き、憤りを哀しみ、痛みを包み込もうとしていた。
ピッ、ピッ、と規則正しい心音が、静けさで支配された部屋に絶え間なく響き続ける。
それだけが唯一、そして僅かな吐息の音のみがこの部屋にある音の全てだった。
淡い月の光の差し込む部屋の中、未央達はぼんやりとした様子で親友の眠るベッドの側に思い思いの恰好で座り込んでいた。
その瞳は確かに開かれてはいるものの、何一つとして現実を映してはいない。
彼らの瞳に――心に映るのは、ほんの数日前までの日常。決して、“今”を映そうとはしていない……深い悲しみゆえに。
まだ“目覚めて”いない患者のベッドにはカーテンがしっかりと引かれ、彼らとを隔てる大きな壁となっている。
今、この部屋にいる中で“目覚めて”いるのは彼女達だけだった。
ベッドの中に眠る少年――淳は、身体中に包帯やテープを巻きつけられ、無数の点滴や輸血のチューブが両の腕から伸びていた。その端整な顔の右頬にも大きめのガーゼが貼り付けられ、そこにはうっすらと赤い血が滲んでいるのを覗く事ができる。肌蹴られたシャツからのぞく胸。その心臓の上の辺りにはいくつものチップが取り付けられ、それはベッドの横に置かれてる大きな機械へと繋がれていた。それは、彼の命をこの世に繋ぎとめるためのもの。
それらは、彼に起きた事の証。彼の痛みを唯一、外の者たちに伝えるもの。
そして彼のその目は、堅く閉ざされたまま。
声は、届かない。決して。
「…………」
口にする言葉も見当たらず、ただ座り込み、そして――想いを、抱いて。
そんな状態がどれほど続いたのか……不意に、未央が顔を上げた。
この部屋唯一の窓枠の下に背を寄りかからせ、じっと淳の顔を見つめていた拓也はそれに気付くとそっと未央の顔を静かに見つめた。
その表情には、何も浮かんでいない。表情豊かな普段の彼らからは、想像も出来ないほどに静かな面差しだった。
淳のベッドの横の床に直接座り込んでいた瞳は、顔を上げることもしなかった。
ベッドの側にあった椅子に座っていた未央は目を閉ざしたまま、天井を見上げた。
やがて、彼女の唇から吐息ともつかない小さなささやきが零れ落ちた。
「……どうして……」
それは小さく、ともすれば聞き逃してしまいそうなほどだったが、それは違う事無く2人の耳へと確実に届けられていっていた。
静けさだけが、彼女の言葉を彩るものとなる。
「……どうして、なんだろうね」
「…………」
――それって、どういう事なの!?
淳の病室から退室し、その後本来の予定通り久々の両親との対面の後。
再会の喜びに溢れていた彼女たちは、すぐに淳の見舞いにとやってきたその場で。浜口医師に、それを聞いていた。……それを、聞かされていた。
あまりの事に、絶望よりも悲しみよりも何よりも、驚きが強くて。
戦慄かせていた唇を動かす事が出来たのは、随分と経ってからだったように思う。
――どうして! だって、帰って来れたって……もう、大丈夫だって事なんでしょ!?
目を真っ赤に充血させ、それとは反対に顔一面を白く青ざめさせながら詰め寄る未央に、彼は辛そうに俯きながら、しかしはっきりと――その残酷な言葉を口にした。
『彼は、今日限りの命だ』と……。
顔を上げたその表情には同様など欠片も浮かんでいなくて。
胸中にある感情を全て、一片足りとも逃さないで隠し通して。
ああ……。きっとこの人は人が死ぬのを何度も経験しているんだろうな……と、瞳は頭のどこかでぼんやりとそんな事を思っていた。
――おそらく今夜が峠だろう。今夜中に意識が戻らなければ……。それに、容態が安定しているのは今だけなんだ。心停止を起こした以上、いつ容態が急変するかわからない……意識が戻れば、まだ希望はあるんだけれど、それもこの怪我では……。
彼は、彼女達から見ればあまりにも残酷な事を、酷く淡々と述べていた。
少しも揺れない静かな口調は、哀しみの裏返しだという事も――理解できなかった。
さらさらと流れる青を纏った銀色の髪を見ながら、拓也はただ呆然とその言葉を聴いていた。思考が働かず、言葉はただ彼の心を素通りしていくだけ――。
――本来であれば、君たちにはこんな事は言わないはずだった。でも、彼のご家族とは誰一人として依然連絡が取れなくてね……酷い事を言っているんだとはわかっている。君たちには酷く残酷な事だろう。でも、それでもどうしても君たちに頼みたい。君たちにしか出来ないんだと思う。……どうか、君たちに
――彼の最後を、看取ってあげて欲しい――
「……馬鹿みたい。“あの時”に横断歩道を渡ってて、車に跳ねられて死にかけて、なんて。そんなの……冗談でもできすぎてるよ……!」
立てた片膝に埋めるようにして顔を押し付ける未央から視線をゆっくりと外し、拓也は壁に寄りかかったまま足を軽く蹴り上げる動作をしてみせた。
それは、無意識の動作。
ボールを蹴る、仕草。拓也はよく、淳と共にサッカーなどをしていた。
日が暮れるまで、朝からずっと飽きもせずに二人でたったひとつのボールを追いまわして。或いは、クラスの友達と一緒に試合のようなものをして。何度勝ちを譲り、負けを悔しがっただろう。
そんな小さな動作の意味に気付いた拓也は、チッと苛立ちを小さな舌打ちで現して足を組替えた。
故意に組んだ両手を目の上に押し当て、視界から全てを塞ぐ。そうする事で、現実から目をそらそうかとするかのように。
「植物状態……か。こんなに包帯でぐるぐるじゃあ、そうなるのかな……」
「……傷自体は、たいしたことないんだって。ただ、頭を強く打ったから……」
ささやくようなその口調は、瞳。
膝の上に置かれた、彼女の握り締めた小さな両手は、込められた力に白く染まっていた。
柔らかに広がったスカートには、すでに幾つもの小さな染みが出来ていた。そして、またひとつ、小さな染みが生まれる。零れ落ちる涙と同じ数だけ。
「私たちは、ちゃんと目覚められた。でも、もしかしたらそれは幸運だったのかもしれないね。淳くんが不幸なんじゃなくて……」
「……なんとか、ならねぇのかな」
今、彼は生きている。呼吸もしている。
なのに、現代の医学ではこれ以上彼にどうする事もできないと言う。
彼を目覚めさせる、ただそれだけの事が。
「……これが、夢だったらいいのに……」
涙と共に零れるのは、決して叶う事は無いとわかっている願い。
それが不可能だということはわかっていても、それでも、願う事をやめる事は出来ない。
夢と仮定し、そして目覚めれば普段通りの日常が広がる――そんな虚しくも切実な願いを、どうして願わずにはいられないだろう?
(夢だったら、っていう仮定は僕も嫌いじゃないよ。でも、今僕らがいるのは夢じゃないだろう? だったらきちんと『現実』を見なきゃ。本の世界のような出来事なんて、そうそう起こらないんだからね)
脳裏に甦るのは、彼の声。いつも何気なく聞いていた、淳の言葉。
いつだったか、彼が同じ様な事を呟いた自分に言ってきた言葉を思い出し、未央は小さな――それこそ今にも消えてしまいそうな、淡い笑みを浮かべた。
(でも……夢の世界のような事、実際に今、起きてるんだよ。だったら少しくらい、奇跡とか……魔法とか、信じてみてもいいじゃない?)
「……魔法とかでさ。あるじゃん? こう、手をかざすと傷が治るってやつ。あんなのが俺たちにもできればいいのにな」
未央が脳裏でささやいた言葉を聞いたかのように、不意に拓也が辛さの混じった苦笑を浮かべながら足元にいる二人に冗談のような言葉を投げかける。
片手を無造作に水平に伸ばし、掌を下に向けている。月明かりが背から照らし、まるでその掌から今にも光が零れそうにも見えた。
そんなふざけた拓也の声に、瞳も顔を俯けたままくすっと笑みを浮かべた。
拓也らしい……。
俯けていた顔を上げ、肩越しに振り返るようにしてそんな動作をしている拓也を瞳は見つめた。
「……ゲームとかであるよね。なんだっけ。確か、『ヒール』とか『キュア』とか言うと、死にかけてたキャラが一瞬で復活するんだよね」
「あれって、よく考えたら詐欺だよな。死んだのになんでそんなに簡単に生き返るんだっての」
「そんな事が出来たら、いいのにね……」
もしそんな事が簡単におきるようなら、この世界はそれこそ大混乱に見舞われるだろう。
だが、誰もそんな事を指摘しようとはしない。
そんな事は、関係無いから。自分たちはただ、願うだけだから。
「もしも今、魔法が使えたら――」
ふと。自らが洩らした呟きに、未央は何か引っ掛かる物を感じた。
今、自分はなんと言った?
少し前にも、同じ様な――それでいて全然違う事を考えなかったか?
モシ アレガ 魔法ダッタノナラ――
口の中が酷く乾いている。寒い訳でもないのに、身体中に鳥肌が立っている。
世界が急に遠ざかり、世界が酷く狭くなったかのような感じがする。
それと相反するように、胸の中に何か、暖かな物があるような気がする。
それは、今生まれたのではなく、ずっと前から存在していたような――
どうして、気付かなかったのだろう。
どうして、試そうとは考えなかったのだろう。
あまりにも、信じられない事だから?
あまりにも、馬鹿馬鹿し過ぎる事だから……?
でも、それがもし――自分の考えている通りだとしたら?
未央は酷くゆっくりとした動作でそっと手を伸ばした。
「……未央?」
その動作に気付いた拓也が小さな疑問の声を上げるが、未央にはそれに答えられるだけの余裕はなかった。
ただ、カタンと音をたてて椅子から滑り落ちると、彼女はそのまま膝立ちの状態で手を伸ばし、目の前にある、ややひんやりとした淳の手を両手で握り締めた。
体温が低い。それでも、確かに鼓動を感じられる。
自分のものよりも若干大きなその掌。それを、両手できつく、きつく握り締めて。
「お願いだから……もし、“アレ”が魔法なら、どうか……!」
湧き上がる火炎。延ばした手から生まれた、紅。うねりを上げる、炎。
一瞬でそれは膨張し、目の前に迫ったソレの体を余す事無く包み込み、そして僅かな消し炭だけを残して消し去る。
それは3人だけの秘密。ありえない、幻のようなこと。
でも、もしそれが事実で、そして自分達が起こした事だったのなら?
それが、姿が変わったのと同様、自分達に新しく宿った影響の一つだとしたら?
それは、『魔法』と呼ばれる物になるのではないか……。
だとしたら、その『力』で彼を救う事ができるのではないか。
そんなあやふやな、ともすれば狂気とも思われる感情だけが今、彼女を支配していた。
闇雲に手を握り締め、涙をぽろぽろと零しながら、ただひたすらに願い続ける。
「お願いだから……!」
「未央……」
そんな未央を辛そうに見つめ、拓也はそっと壁から背を離す。そして、床に膝立ちになっている未央の側に行き、その横に片膝を立てて座りながらそっと振るえる少女の肩を抱きしめた。
未央の泣き顔を自分の未だ薄い胸板に押し付け、頭を軽く押さえてやる。
そうする事で、少しでも彼女が救われるように。そして、自らもその小さな温もりを求めて。
「未央……いいから」
「……どうして……あの時は、できたのに……どうして、ダメなの……?」
「……未央ちゃん」
そっと、瞳も手を伸ばす。そして淳の手を握り締めている未央の両手を包むようにして小さなその手を重ねた。
この温もりが、少しでも彼女を癒してくれるように……。
そうする事で、自分の哀しみが溶けていけるように。ともすれば狂気に沈みそうになる自分を、確かな現実に繋ぎとめるために。
誰かを支える事など、できはしないから。だから、自分たちはこうして支え、支えられていくしか出来ない。誰かを支えられるほど、自分たちは強くはないのだから。
「哀しいよ……どうして、こんなになっちゃうんだろうね……」
「何もしてないのに、さ……コイツ、まだ自分の顔みてないだろ。見たら、きっと驚くのにな」
冗談交じりの声。しかし彼の表情は哀しみに彩られ、その右目からは一筋の涙が零れだしていた。
そっと目を閉じ、小さく刻まれる鼓動だけに耳を澄まして。
「……どう、して……」
そして、未央は今はただ、淳の手を握り締めて涙を流していた。堅く瞼を閉ざし、何も出来ない自分にたとえ様の無い悔しさだけを感じて。
何も出来ない。何もしてあげられない。
ただ、こうしてみているだけしか、出来ない。
自分が無力なのだと、初めて心から思う。どうして、自分達には『何か』を成し遂げられる力がないのだろう。それがあれば――。
いつしかそっと身を寄せ合った彼らは、ただ静かに涙を流し続けていた。
そして、それからどれだけの時が経ったのか――いつしか未央は小さな声で何かを囁いていた。
「
……thought……not……theeir game……I……」
ふと、聞こえたその"歌"に拓也と瞳は何も言わずに静かに耳を澄ました。懐かしい思いが、暖かなものとなって彼らの心を満たしていく。
それは、その途切れ途切れの旋律は、彼らが何度も耳にしていた"歌"だ。
いつだったか――淳が貸した数枚のCDアルバムの中から、未央が気に入ったと言ったその曲を皆で聞かされた事があった。
未央は気に入ったから、また貸してねとにこにこと笑い、そのCDケースをしっかりと抱きしめていたのを思い出す。あの時はこの曲のどこが気に入ったのだろうと思っていた。
(綺麗な歌でしょ? 和訳の方もあるんだけど、あたしはこっちが好きなの。誰だか知らない、でも大切な人に『あなたは一人じゃないよ』って言っている歌なんだよ)
そう言って、笑って……あの時は拓也も瞳も、そして淳もおかしそうに笑っていた。誰も、その歌にそこまで魅力があるとは思えなかったから。
でも、今ならわかる。静かなそのメロディーは心に直接響き、優しく愛撫していく。
未央はいつしか、涙を流しながらそっとその歌を口ずさんでいた。時折言葉をつっかえさせながら、そのメロディーを奏でていく。
「
……And if you should still……into despair……」
歌と共に流れる、小さな――眩いほどに輝きつづける、思い出が彼らの心を揺さぶっていく。
他愛の無い、けれど大切な思い出達。
(これ、未央は歌わないの?)
(ええ? だって英語だもん。難しいよ)
(やればできると思うよ。聞いてみたいな。ねぇ、歌ってみなよ)
(未央ちゃん、歌上手だもんね。私も聞きたいな!)
(やってみればいいじゃん)
冗談半分にみんなで急き立てられ、それもいいかな、と思って。そして何度もCDを聞いて覚え――まだ、彼に聞いてもらっていないのに。
もうすぐ、彼の誕生日だった。
瞳と拓也と3人で、お金で買わないプレゼントを渡そう、と言って……約束して。彼がプレゼントと名の付く物を好まないのを見越してのアイデアだった。
拓也は自分で釣って来た魚の料理を作り、瞳はメインの大きなケーキを作る。
そして未央はちょっと照れくさいけど、その歌を彼に聞かそうと思っていた。
飾りつけなどはないけれど、それでも心を込めて……大切な親友に渡す筈だった、プレゼント。
(起きてよ……お願いだから……誰か……神様……!)
数え切れないほどの、何度目かの涙。それが、零れて重ねられた掌に当たった、その瞬間。
「……えっ……?」
ふわぁっと、自分の体の中から暖かな物が溢れ出したのを、未央は感じた。それは確かな存在感を放ち、トクントクンと優しい鼓動を繰り返していく。
そしてそれは次第に大きくなり、拓也と瞳にも同じ現象を起こさせていた。
「……な、なんだ……?」
「……うそ……光ってる……!?」
暖かなものが零れる、と思った瞬間にそれは体全体を包み込み、未央の体を淡い光で包み込んだ。
それを目にした瞳は驚愕に目を見開き、拓也は体内に生まれた熱に戸惑っていた。
「な、何……これ……?」
その光は次第にしっかりとした色を持ち、彼女の全身を優しく包んでいく。指先から頭、つま先までをしっかりと包み、蒼い色をもったそれはやがてすっぽりと彼女を覆うと安定したかのように動きを止める。
「どうして……まさか、本当に魔法が?」
「……そんな、馬鹿な……」
「あ、拓也くん!」
瞳の声に拓也はビクッとし、慌てて未央を抱きしめていた腕を見つめる。
彼の全身は未央と同じ様な淡い光に包まれだしていた。それもまた静かな脈動を繰り返し、そっと彼を優しく包み込もうとしている。それは、淡いグリーンの色を持っていた。
そしてまた、瞳も同じ様な光に包まれていた。彼女はうっすらとした赤い色だ。
そのどれもが優しい色をして、決して危険なのではないのだという事を彼らに知らしめている。
「まさか……本当に!?」
「これって夢じゃないよね……まさか……魔法、なの?」
戸惑いの声を上げながら辺りを見渡した瞳は、それが放つ光で辺りのものが3色の色を映しているのを目にして、戸惑いの色を深くする。
そして拓也は驚きながらもソレがなんであるのかを確かめようと、じっと己の空いている右手をきゅっと握り締めていた。
「これは……奇跡……魔法、なの……か……?」
「……なんでもいいよ……なんでもいいから……お願いだから、淳を……!」
最初は戸惑っていた未央も、すぐにはっとすると今まで以上の力と願いを込めて、淳の手を堅く握り直した。そして瞳の手が乗せられたままのそれをそっと自分の額に押し当てる。
今になって、彼らはすぐ隣にあった機械からピーッという音が流れているのに気がつく。
しかし、そんなことは今は関係なかった。
今の自分達ならば、平気だと――心の何処かで、彼らは知っていたのだから。
意識するまでも無く、彼らは当然のように手を重ねあった。
そこに、自分達の内に芽生えた“モノ”を集中するようにする。そうするのだと、わかった。そして、強く――今まで以上に、強く願った。
それはありはしない神などではなく、確かにそこにある、自分達の持つ『力』に――。
(帰ってきて……そして、笑って? いつものように)
(俺たちはいつだって一緒だろう? だから、戻ってこいよ……ここに)
(お願いだから……『また』別れるのは、嫌だから。どうか)
「淳……!」
重なり会う、言葉。そして目覚めた力は、彼らの願ったそのままに働いた。
掌に集まったその力は、彼らの繋がった体を介して淳へと巡り、彼の体をそっと光で包み込んでいく。それはやがて赤・緑・蒼と変化した後、じっくりと時間をかけて薄紫色へと変わる。
その"色"こそが彼に最も相応しいと、彼らは何の疑問にも思わずにそう感じた。
それはそっと彼を包む。淳の青銀色の髪がゆるくなびき、そして彼の体を静かに癒していく。
「…………」
目に見える変化はない。けれど、確かに彼らの持つ"力"は彼を癒し、そして――。
ピッ、ピッ、ピッ、ピッ……
未央達の体を包んでいた光が消えると、それを待っていたかのように生命維持装置が静かな鼓動を彼らに教えるように鳴り出す。
脱力感に包まれていた未央は、それをぼんやりと見返す。そして、気付けば僅かながら暖かさを取り戻した手を感じ取り、やっと小さな呟きを零した。
「……え……?」
それを聞き遂げ、未央同様呆然としていた拓也は慌てて淳の顔を見直した。
彼の顔色は、さきほどとは違った温かみを感じさせる白へと変わっていた。
「お、おい……これって……」
「……息、してるよ……!」
ゆるゆると、眠り続ける少年の口元へと手をやった瞳が、涙を溢れさせながら、言う。ふらっと身体をよろめかせ、力の入らない腕をベッドに押し当て、なんとか体が倒れるのを防ぎ。
かくん、と拓也が力が抜けたかのように床へと膝をつく。ほっと顔一面に安堵の色を浮かべ、力なく床へと直接座りこむ。
呆然としたような表情をした未央は、ほけっとしたまま拓也同様床に直接座りこむ。
彼らの顔はその表情とは裏腹に蒼白になり、紙のように白い。ぐったりとした態度は疲れ切ったかのようで、どこからどう見ても、尋常ならざる様子にしか見えない。
だが、誰一人として、自分達の状態に気づく事はない。彼らが見つめるのは、今、確かに息を吹き返した一人の少年の姿。
大切な、仲間。これまでも、そしてこれからも共にあると願った親友。
体の奥深くから迸った『何か』の余韻に息をわずかに弾ませながら、未央はそっと涙を零した。
喜びと、そして。自分でもよくわからない感情に。
自分達から生まれ出た、新しい『ちから』に。
「……よかっ……た……」
唇から言葉が零れ。そして、未央はぐらっと身体をよろめかせ、ベッドに倒れこむ。
その様子を目にし、驚いたようにしながら手を差し伸べようとした拓也もまた、視線を彷徨わせて再び床へと座りこんでしまう。
(……あ……れ……?)
自分の身体に起こった事がよくわからなくて、未央は身体を起こそうともがき――そして、身体が全く自分の言う事を聞かない事に気付いた。それどころか、ゆっくりと視界が暗くなってゆく。
定まらない視線を必死にかき集め、隣にいたはずの瞳へと向けると彼女もまた、床に倒れ臥している。渾身の力を込めてわずかに顔の向きを変えると、反対側で拓也がぐったりとした様子で座りこんでいる。俯けた顔。
ゆっくりと、重い虚脱感が全身を支配していく。瞼が重くて、とても耐え切れない。
例え様のない恐怖が胸に溢れ、それに強い戸惑いを覚え。視界が完全に暗闇に支配される前、最後に目にしたのは、そっと横たわった友の姿。
それにほんの少しだけ安堵を覚え、そして。
未央はついに、意識を手放した。
――nothing is braver thanhonesty,my life is your faith in me――
l'llbe there when you need
you don't have to hide from me
what you are feeling now
I fill your soul……
♪by Maaya Sakamoto, Shanti Snyder