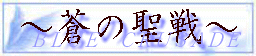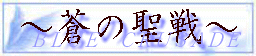――恋焦がれるは 遥かなる思い出
願い求めるは 新たなる温もり――
目覚めを望んで、瞼に浮かぶ姿に願う
それはいつの事であるのかを
穏やかな日差しが、部屋一杯に差し込んでいる。
柔らかな風がカーテンを揺らし、新鮮な空気を運び込んでくる。
だが、その空気に混じるかすかな"におい"に、誰が気付くのか。
怠惰なる平和のみの今の時代を生きる人々には、それすらも知ることは無く――。
キィ、と小さな音をたてて病室のドアが開く。
そこから顔を覗かせるのは、まだ三十路には手が届いていないだろう年齢の白衣を纏う一人の青年。キラリと一瞬、光を反射したネームプレートには『浜口正樹』と刻まれている。
まだ年若く見られる彼はしかし、年齢に見合わずかなり高度な技術を持ち、多くの者達からも一目置かれる存在だった。だからこそ、多くの先輩医師と共にこの患者達を受け持った。
――だが、と彼は思わずにはいられない。
「お邪魔するよ……」
小さく声をかけ、足音を忍ばせながら窓際のベッドまで足を運ぶ。その一歩手前で彼――浜口は歩みを止め――小さな笑みを浮かべた。
揺らめくカーテンから零れ落ちた柔らかな光を受ける、まっさらなベッド。
そこには、つい先日生死の境を彷徨った一人の少年が横たわっている。
彼は何時死んでもおかしくないはずの状態から、一体どういった奇蹟からか一命を取り留めた。それだけでなく、昨夜より驚異的な回復力を見せている。
現代医学では考えられないほどの、だ。
異常だと言っても過言ではないほどのこれを目にしたのが、もし自分ではなけでばどうなっていただろう。浜口はいつしか、皮肉な気分で口唇を歪めていた。
この様子ならそう遠からぬうちに退院できるだろう、とは思う。
確かの彼の回復スピードには目を見張るものがある。本来ならもっときちんと調査をしたいと思うが――今はそれよりも優先すべき事が山のようにある。彼だけに構っているような暇はないのだ、幸いな事に。
もし誰か他の医師たちが彼の回復力に気付き、徹底的な検査をするとなるとまず彼は自由がなくなるだろう。まだ年若い少年にとって、それではあまりに可愛そうだろう。そうならないようにある程度の細工をし、居合わせた看護婦達に口止めをした以上大丈夫だとは思うが。
(でも……)
問題があるとすれば、“あの夜”から二日がたった今もまだ彼が目覚めない事、か。
容態は安定しているし、順調に回復している。このぶんなら何の心配も無いし、目覚めないとはいってもまだ2日目だ。そんなに心配するほどでもない。
本当の問題は、彼の家族の事だ。
小さく溜息を洩らすと軽く頭を振ってそれらを頭の片隅へとおいやる。そして浜口は気を取り直してそっと手を伸ばし――わずかに迷ってから、一番近くにいた少年の肩をゆする。
「……こらこら、キミたち。ここにいるのは構わないといったが、ここで寝ては風邪をひくよ? それに、食事はきちんと部屋で取ると約束しただろう。もう起きるんだ」
「ぅん……あー……」
目の前にあるベッドに上体を被せるようにして眠っていた少年の肩をゆする。
少年はぱちぱちっと目を瞬き、寝そべったまま顔だけを上げて自分を起こした張本人を見上げた。
「……浜口先生?」
「そうだよ、拓也君。ほら、そろそろ昼食の時間だ。一度戻りなさい」
赤茶色の髪が揺れ、シーツのあとがついた頬のまま目を擦っている拓也が身体を起こしながら腕を伸ばして大きな欠伸をした。ぼさぼさの頭を振りながら、気だるげに片手を伸ばす。
そこにも、先程の拓也と同じ様に壁に背を預けて眠りについていた少女が一人いた。その肩を遠慮のない仕草でゆすりながら、声をかける。
「瞳、起きろよ。そろそろメシだってさ」
「……ん」
眠そうな声を出す瞳を見て、さらに強く肩をゆすりながら次に拓也はもう一人の少女に手を伸ばした。その少女は、拓也達がいるのとは反対側からベッドに頭を預けていた。
先ほどから浜口が声をかけていたのだが、彼女は全く起きる様子がなかった。
「未央ちゃん、ほら、そろそろ起きなさい」
浜口の声にも反応せず、くぅくぅと小さな寝息を立てている少女の髪を拓也は伸ばした手で軽くぴっぱる。それを邪魔そうに顔を振る少女の様子を横目で見ながら、浜口は軽く溜息を零す。
腰に手をあて、軽く息を吸い込む。くちびるには、笑み。
「ほら。……いい加減に起きないと、二度とここに入れないようにするぞ?」
「嘘ッ!」
「それはダメッ!」
浜口医師が口にした一言であっさりと眠りを堪能していた二人の少女は一瞬にして飛び上がり、大きな声で叫んだ。素早い動作で、必死の表情を浮かべながら立ち上がる。
そんな二人を見て、くくっと拓也は喉の奥で笑った。きょとん、とした表情のまま、浜口の顔を見上げ、そこにも笑みが浮かんでいるのを見た未央と瞳は、やっと自分達がからかわれたのだと理解する。
くく、とくちびるを振るわせつつ、驚いた表情を浮かべたままの二人に浜口は口を開く。
「大丈夫、冗談だよ」
「え……やだ、先生ひどーい!」
「あー……良かった……」
ぷくっと頬を膨らます瞳に、安堵の吐息を洩らす未央。
傍でそれを見ていた拓也はまだ楽しげに笑みを浮かべている。彼は最初から浜口の言った言葉が冗談だとわかっていたので、尚更驚かされた二人の様子がおかしく感じられた。
小さく笑っている拓也を横目で見やり、瞳はむぅ、と眉を寄せた。
「いつまでも笑ってないでよぅ」
「わ、わる……ぷっ」
「態度がわるーい!」
大して力の入っていないチョップを繰り出す瞳から逃げるように身を捩る拓也を苦笑交じりに見つつ、未央は再び生欠伸を洩らした。
寝たりないように眉を顰めながら、気だるげに肩を何度も回している少女の様子に、浜口は医師としての視点で気が付く。
「どうかしたかい?」
「ん……なんかちょっとだるくて。疲れてる感じが抜けないみたいな……?」
考えるように間を置いてからそう答えた未央は、真剣な表情をして自分を見ている若き医師の視線に気付き、すぐに笑みを浮かべてみせた。
ゆるく首を振り、
「大丈夫です。たぶん、慣れない病院生活でちょっと疲れただけだと思うから」
「そうかい? ならいいが……何か変な事があれば、必ず僕や看護婦に言う事。君たちもだよ?」
「はーい」
「わかってまーす」
元気よく返事を返した二人の様子に頷き、彼はふと思いついたような動作で右手の手首を見る。――正確には、そこにある腕時計を。
その針がすでに12を指そうとしているのを見やり、若干慌てたように彼は顔を上げる。
「ほら、もう昼食を配り始めているよ。一度部屋に戻って、それからまた来ればいいだろう。午後にはご家族も見えるだろうし」
「あ、そっか! じゃあいったん戻ります。……ほら、行こう!」
「おっけ。じゃあ、また来るからなー、淳!」
「またあとでね!」
楽しげに走っていく少年達に「走らない事!」声をかけながら、彼は小さく笑みを浮かべた。
ああしている分には、全く普通と変わらない。若干年齢よりも幼く思えるほどだ。
しかし、子供達が元気な様子を見るのは病院に勤めるものとして最も嬉しい事ともいえる。親しくなった患者が退院していくのは寂しいが、それが何よりも喜ばしい事だと、知っている。
でも――……。
「……彼らの場合は、どうなんだろうな……」
この病室にいる人々のほとんどが“眠り”についている――今ではついていた、といえる――のを知っているからこそ。
外の様子を少しなりとも知っているからこそ、彼はその場所で小さく呟いていた。
これからあの若者達の身に起きるかもしれない事を、そっとひとり胸のうちにしまいこむ。
どうなるかはまだ、わからないのだから。
「……キミは、もしかしたら幸運なのかもしれない……」
眠りについている少年に向かい、小さく囁く。
それは、そう思うことは医師としては失格なのかもしれない。けれど、確かな彼の本心だから。
小さく溜息を洩らし、一人佇む病室を見渡す。
淳を含め、ここにいるのは全員が今だに“眠り”につき、なおかつある共通した問題をもつ者達だ。
早く目覚めて欲しいと思う半面、このまま目覚めない方が――と思ってしまう。
「ダメだな、こんな事を考えるようじゃ。そういえば、しばらく休暇をとってなかったからなぁ」
冗談混じりの口調で呟き、彼はクリップボードを持ち直して淳の枕もとへと足を進めた。
「はい。今日の昼食よ」
そう言って看護婦から手渡されたトレイの上の料理をみて、未央は顔を輝かせた。
「あ、魚の煮付けだー♪ お味噌汁もあるー!」
「え、うそっ。……あ、ほんとだ! やだな、魚嫌いなのに」
「大丈夫。あとで貰ってあげるから」
嬉しそうな声を上げる少女達の様子に小さく笑みを洩らし、二人の母親ほどの年齢の看護婦はテキパキと他の患者の分のトレイを手に持つ。
それを持っていこうとして、ふと思い出したように振り返っていそいそとベッドへと戻ろうとした未央を呼び止める。
「それじゃ、いつものように食器はきちんと返してちょうだいね。前みたいに、机におきっぱなしにされるとあとで困るのは私たちなんだから」
「はーい。気を付けます」
「あ、待ってよ、未央ちゃん!」
そう答え、未央は瞳を置いてさっとベッドへと戻っていく。その後を瞳が追いかける。
未央達は現在大部屋にいる。正確に言えば、6人部屋に無理矢理入っている状態だ。
以前は個室に入れられていたが、『謎の症状』で倒れた人々が毎日運び込まれる中で、個室を一人で使わせるような余裕はなくなったらしい。
彼女達3人が入れられていた個室は、現在は2〜3人前後の人が使っているらしい。
元は6人いた部屋に付き添い用の簡易ベッドを運び込み、だいたい7人から8人程度の患者を詰め込むようにしているのが現状だ。
まぁ、女性だけの部屋だから遠慮はいらないし、この病室にいる者たちはまだ眠っているので深夜でもいくら話しても怒られる事はない。それを思えば、むしろ個室の時よりも便利だと、彼らは考えていた。……男だと言う事で、別の大部屋に入れられた拓也は別として。
とりあえず、最初からあったベッドの隣に付き添い用のベッドをおき、その二つを未央と瞳に割り当てられている。うるさいのはまとめて、ということなのかもしれない。
――ちなみに、向かいのベッドも同じ使用にされている。そこには姉妹で“眠って”いる二人がいるらしい。もっとも、カーテンが引かれているので確認はしていないのだけれど。
拓也も部屋は違うが、同じようにしているらしい。彼は幸いきちんとしたベッドを使用できているらしいが、彼の部屋にも付き添い用のベッドを使っているらしい。もちろん、そのベッドの使用者はまだ“眠って”いる。
「ちわーっす! お邪魔しまーす」
「拓也くん、遅いっ!」
「ほんと。もう食べちゃおうかなって思ってたんだけど?」
「げっ。悪い悪い。でも、そんなに遅れたわけでもないだろ」
昼食の載せられたトレイを手にした拓也が、スライドさせたドアを閉めて中に入ってくる。
この部屋割りになってから、自然と彼らは同じ病室で食事をするようになっている。病室もそんなに離れていないため、トレイを持っていけば事足りるのだ。朝食は未央達が移動したから、昼食は拓也が移動する。なんとはなしに、そんな風になっているのだ。
ベッドに座り、備え付けのテーブルに二人分のトレイを置いていた未央達を見やり、拓也は空いているスペースに自分の分のトレイを置くとイスをひっぱってきて、座る。
「んじゃ、食べよーぜ」
「もち。いっただっきまーす」
「いただきます」
瞳は軽く手を合せ、箸を手にして食事を始める。しばらくは言葉もなく、食事だけに口を使っていた。話しながら食べるのは楽しいが、時間を無駄にはしたくない。
あらかたの皿を空にしてから、やっと拓也が口を開く。
「……でもさ、意外だよな? 今日も俺の部屋、誰も起きてないんだ」
「ん……こっちも。ほら、全部カーテンがかかってるでしょ?」
口の中にあったほうれんそうを飲み込み、未央も拓也の言葉に頷いてみせる。
ちら、と視線は向かいのベッドへと向かっている。そこで眠っている人。彼女達も、まだ、起きてくる気配は無い。毎夜毎夜、呼びかけてはいるのだけれど。
しんとした、病室。それは少しだけ怖くて、悲しい。
「もっとどんどん起きてくるかと思ったんだけどね」
「起きてくる人、いないわけじゃないみたいだよ」
と、こちらは先程まで魚の煮付けに苦心していた瞳。彼女は諦めたかのように箸を置いて、魚の乗った皿をそっと拓也のトレイへと乗せながら口を開く。
「さっきもトイレに行った時に見たよ?“目覚めて”た人。えっとね、空色の髪の男の子。隣のトイレに入っていったから、たぶんもう起きて一日以上経ってたんじゃないかな?」
「でも、そんなに多くはないみたいだよね。一つの病室に1、2人もいないみたいだし」
「未央や俺たちが起きたのは最初で、それから少しずつおきてきてるってとこかな?」
瞳がよこしてきた煮魚に特に疑問を持つこともなく、ごく自然に箸をつけつつ、考え込むように軽く首をかしげる拓也。あとで分けてもらおう、と味噌汁を飲んでいた未央は思った。
最後に残っていたご飯を飲み込み、瞳がゆっくりと口を開く。
「でも、看護婦さんに聞いたらだいたい……一日に7、8人くらいずつ、起きてるんだって。検査で2日くらいは絶対に病院から出られないけど、検査が済んだ人はもう退院も出来るんだって。入院する人が多いから、あんまり長くは入れておけないみたい。私たちがなかなか退院できなかったのは、貧血気味だったからちょっと念入りに検査したからなんだって」
あっけらかんと瞳が告げる言葉を聞いて、ぎょっとしたように拓也と未央は身を引いた。
――二人がどれだけ尋ねても、絶対に何も答えてくれなかったのに。
「……どうやって聞いたんだ? そんなこと」
「ナイショに決まってるでしょ♪」
にこやかに微笑みながら楽しげに答える瞳に、二人は訝しげな視線を送ってみせた。
時々使われる瞳の「ナイショ」は、誰にも言えないような事をしたか、それとも……。
「まあ、気にするだけ無駄だし」
「いつものことだしね」
さきほどまでの態度をあっさりと拭い捨て、さらりっと納得したようにコクコクと頷くと彼らは再び箸を動かしだした。
また黙々と食事を続け、やがて全ての食器が空になる。カラン、と軽い音が静かな病室に響き渡った。しかし、それでも誰も口を開こうとしない。
生暖かいお茶が入っているカップを両手で包むようにして持ちながら、知らず知らずのうちに未央は決して小さくはない溜息を付いていた。
拓也はコト、と音をたてて箸をトレイに置く。せっかくの好物である魚の煮付けも、最後は美味しく感じられなくなっていた。
「……いつ、起きると思う?」
「さぁ。いつも寝起きはよかったけど……どう、なんだろうな……」
小さな呟きは、同じ様な囁きでもって答えられた。
ばさっと音をたてて瞳が髪を結っていた紐をはずす。普通はゴムを使うが、平均よりも長い彼女の髪ではゴムよりも結い紐を使った方が楽らしい。
長い髪を軽く振り、右手のてのひらでそっと己の髪をひと房すくい上げる。
さら、と音をたてて彼女の光沢ある髪はゆっくりとてのひらを滑り、流れ落ちる。光を放つその髪は、美しい緑の黒髪。深緑色。光沢あるツヤが、一際目をひく。
「先生はもう異常はないって言ってたでしょ? 植物状態になったわけでもないって」
「うん。たぶん、まだ疲労が抜けてないから目覚めないだけだって言ってた。……でも」
「もう、2日。それともまだ2日、なのかな……」
そっと伏せた目を閉ざし、己のうちに沈み込む3人。
すっと目を開き、顔を上げる。瞳はその長い髪を再び纏め、細長い紐で結びなおした。
溜息をもらす。ここでこうしていたとしても、何も変わらない。変わりようが、ない。
「……いこっか。淳も待ってるよ」
「じゃあ食器、片付けよ? 全部纏めて」
「んじゃ、俺が机仕舞う」
カチャカチャと音をたて、食器をテーブルを片付ける。この病院で一緒に食事をするようになってからやっている、同じ動作。3人とも手馴れたものだ。
ドアを開き、廊下に出してある大きなワゴンに3人分の食器を乗せると、彼らは歩き出した。
もう、通いなれた廊下。同じ道筋。
そして、その先にある光景も――。
「これでさ、ドア開けたら淳が起きてて『おはよう』とか言ったらどうする?」
未央達のペースにあわせて歩きながら冗談混じりの声で言う拓也に、う〜ん、と真面目な表情で考え出す瞳。それを見て苦笑気味に手を振ったのは、未央。
「ないない、淳はそんな事言わないって。言うとしたら――うーん、なんだかとんでもなくまともな事を言うんじゃない?」
「でも、淳くんって時々すごく変な事、言い出すじゃない? なんか想像しにくいんだよね」
「ああ、そういえば。……前なんか、道に落ちてた100円玉見て唐突に『警察ってやだよね』なんて言い出したな」
「うわー。何それ。意味わかんないよ……」
「普通に考えて普通に言った、とかいってたけど。どっかぶっとんでんだよなぁ、あいつ」
「頭がいい人の考える事なんて、わかんないって」
「起きてたら何を言うかなぁ……」
「まだ考えてるの、瞳?」
くすくすと笑い、目の前に迫った病室のドアに手を伸ばし、
ガチャ
「っわ!」
「え?」
中から開いた扉。驚きに固まる3人に、ゆっくりとドアは開いていき――。
一人の少年が、姿を現した。
「……あれ?」
目の前には、輝く銀。青みを帯びた髪が、さらりと揺れる。
見慣れた顔立ち。つい先ほどまですぐそばで見つめていた顔が、驚きの表情を浮かべていて。
その瞳にうつるのは、呆然とした表情の自分達。
驚いた事に、彼が纏うその色は『薄紫』と『金』の2色。
「うそ……」
感極まった瞳が、口を押さえて小さく呟く。その頬を涙が伝い、零れる。
彼の表情に浮かんでいた驚きが、ゆっくりと困惑に変わる。困ったように眉を寄せ、軽く頬をかく、その仕草。
――生きていると、目覚めているという、その証。
「えっと……その、君たち、誰?」
紡がれるその言葉。ずっと聞きたいと思っていた、その声。
流れ落ちる涙をそのままに、なんとか笑みらしきものを浮かべた未央はそっと手を伸ばした。
「……ひさしぶり、淳」
――手に触れたるは 冷たきてのひら
握りかえせしは 暖かなまなざし――
もう、2度と手放しはしないから
だから、どうか取り上げないで
なくしたはずの心さえ、失ってしまうから