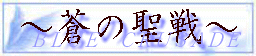
第三章 〜現れるもの〜
【1】
|
明るく光る宝石と 冷たく光る剣を持ち 先へと向かって走り出す でも 忘れてはいけないよ あなたに潜む感情を 狂気も全てが現実で あなたの欠片であることを やわらかに漂うひかり。 いくつもの色と、形と、大きさとをもつそれらが辺りを囲む。 ゆるやかな軌跡を描きながら浮かぶひかりに、ふと笑みが零れた。 優しさが滲み出すような、そんな暖かさを感じる。 生まれる前、覚えてもいない母の胎内に守られていたころのような。 眠りのように深いところへと沈もうとした、その時。 突如、風に吹き飛ばされたかのようにそれらは一瞬にして消え失せた。 消え失せたものの変わりに、痛みさえ感じるほどに暗く淀んだ色彩が現れる。 ――なに? 包み込むひかりは、いつしかやみへと移り変わっている。 けれど、それは禍々しさを感じさせるのではなく、それを知らせようとしているかのよう。 纏い、浮かべる色がけが違うひかりとやみ。 ――なにか、あるの? 問いかけ、答えを探そうと意識を凝らし、目を瞬く。 けれど、それよりも先に。 予感を掴もうとするよりも前に、ぴしゃり何かが途切れるような感覚が叩きつけられる。 そして。 「…………」 ぼんやりとした視界に天井を収め、未央はゆっくりと息を吸い込んだ。 目に映る天井に不思議と懐かしく、けれど見慣れた感覚を覚えてふと首をかしげた。 しばし眠気の残る目を瞬きながら考え、未央はあぁ、と息をついた。 (そっか……帰ってきたんだ) どこか懐かしいその空気は、それもそのはず、慣れ親しんだ自分の部屋のものなのだから。 ――昨日。 未央は、およそ2週間ぶりに自宅へと帰ってきた。 親友達とは翌日に連絡をとる約束を交わし、両親と共に久しぶりになる自宅へと戻ってきた。 頼み込んで湯船を張ってもらい、病院にいるあいだに染み付いてしまった薬品の匂いを入念に消して食事をし、必要最低限の会話をしただけですぐに日の高いうちから眠りについてしまった。 帰ってきたという実感はないに等しく、今こうして目覚めてやっとそれに思い至ったようなものだ。 「あ〜……今、何時だろ……」 長時間寝ていたためか、乾燥してカサカサする喉を抑えながら枕もとの時計へと手を伸ばした。 しばらく手を彷徨わせ、やがて覚えのある感触にそれを掴み、引き寄せて文字盤に目をやる。時刻は6時をすぎたところだった。 静かな部屋に、小さく時計の針が動く音が響く。 カーテンを引いた窓からはうすぼんやりとした光がさしている。あまり見慣れない、早朝の光景だ。 昨夜は6時になる前に横になってしまったから、12時間はたっぷりと寝ていたことになる。 「うわ〜……寝すぎだよ、これは……」 まだ朝早いが、これだけの睡眠をとった後では寝直すことなどできない。しかたなく、未央はまだ寝ているだろう両親を起こさないよう、物音に注意しながらベッドから下りた。 ひたひたとフローリングの床を歩き、カーテンの隙間からほんの少しだけ顔を覗かせる。 懐かしく、変わらない町並みが目の前に広がっている。 早朝だからか、人通りのない町は早朝特有のあさもやに包まれ、ゆっくりと目覚めようとしているかのようだ。――その、当たり前の日常の中に見え隠れする、違和感。 かすかな溜息を零し、未央はガラスに映った自分自身の姿に目を細める。 (きんいろ……というよりレモン色の、髪。それに、あおい……蒼の、瞳) コツン、と額をガラスに押し当てる。すぐにさらりとした感触と共に髪が流れ落ちてくる。 視線を奪う、鮮やかな色。それを見たくなくて、未央はしっかりと瞼を閉ざした。 「……何よ、これ……」 自分の中に、確かな”異”がある。 それは”違和感”であり、”異質”であり、”異常”でもある。 それは一部は目に見えるものであり、そしてまた、自分と親友達4人だけが知っているものでもある。 何よりも恐ろしいと思うのは、それが自分自身の中にあることが、あることこそが正常なのだと告げる、自分自身の心だった。 今更、と思う。 何故今ごろ、とも思う。 目覚めてから今日まで、考える時間は少なくなかった。なのに、今になってこんなことを考えるのは――自分の場所ともいえるところに帰ってきたから。 未央の、自分にとってのテリトリーとも言える場所。そこに戻ったからこそ、やっと考えることができるようになったのだろう。 今までは、言ってみれば”全て”が異常だった。 目覚めて見た場所、起きた変化と事態、その全てが未央にとって平常とはかけ離れたものであったが為に返ってそれを「異常」だと考えられなくなっていたのだ。 それが、自分のテリトリーである自宅に戻り、一晩時間を置いたことでそれらを改めて見つめ直すことができた。 ――だからこその、恐怖。 「瞳……拓也……淳……」 かけがえのない親友であり仲間である3人を想い、心細く感じながら彼らの名を呼んだ。 脳裏に彼らの姿が浮かぶ。 その彼らは、前とは違いさまざまな色彩を纏って現れた。それがすんなりと思い描けることが、未央にとってそれこそが現実なのだ、と自分自身に改めて突きつけられたようで、つらい。 そっと唇に歯をあて、目を開けてどことも知れぬところをきつく睨み据えた。 しばし迷ってから、そっと窓を開ける。 「……さむ……」 朝特有の、冷たい風がそっと未央を撫でていく。その感触を感じながら、未央はじっと佇んでいた。 どれほど外を見つめていたのだろう。 体がすっかりと冷え切り、それに相反するように日差しが徐々に熱を帯びてくるころ、未央はやっと動き出した。 大きく開いていた窓はそのままに、カーテンを引いて日差しを遮り、ゆっくりとした足取りでベッドに近づき、腰掛けた。 「…………」 しらず、溜息が零れる。 どっしりと重く感じられる体を支える努力を放棄し、そのままとさりと軽い音を立てて布団の上に横になった。窓を開けていたせいだろう、体も布団も冷たく、それが気持ちよかった。 視線を横に動かす。 ベッドサイドにあった数枚の写真。その中の一枚に視線を奪われた。 「……真吾……」 それは、未央の隣で笑っている、やや幼い少年。 たったひとりの、弟。 「まさか、真吾もなんて……思ってもみなかったな……」 昨日両親と交わした数少ない会話のなかで、教えられていた。 『真吾もお前と同じようになって……今は、別の病院にいる。目が覚めるのが遅かったから退院するのは明後日以降になるらしいが』 『あの子に怪我はないの。様子を見に行ったけど、元気そうだったから心配は要らないわ』 その言葉は嘘ではない、と思う。でも、だからといって安心できるわけではない。 それに。 「父さんも母さんも……あたしも、どうしたっていままでどおりじゃいられない」 自分達の子供の容姿が変わったことで、何か拒否されたわけでも、嫌悪されたわけでもない。ただ、どうしても不安と戸惑いをなくすことは出来なかった。 そのため、昨日は僅かに言葉を交わしただけで部屋に来てしまった。 疲れてもいたし、考えたいこともあったから。 「……ほんと、なんなのかな。あたしも拓也たちも真吾もこんなになるし、あの隕石っぽいのは何かもわからないし、それに――」 ふと、口を紡ぐ。 昨夜、両親が教えてくれたのは大きく分けて3つ。 弟の真吾も未央と同じような状態になっていること。世間は一応平常どおり機能し始め、学校のみが幼稚園から大学まで全て休校になっていること。 そして――謎の生物らしきものが現れたこと。 正体どころか、どこから現れどこに消えているのかも判らないそれは、突如現れては破壊の限りを尽くし、または人を襲い、消えていくのだという。 間違いようもなくそれはあの病室でみた化け物のことだろう。 未央たちが倒れ、変化したのとその化け物たちが現れだしたのは、おそらくほぼ同じころ。 それは、いったいどういう符号なのか。 両親は言葉を濁したが、きっと未央がそう考えたように、彼らもまた、その二つが決して無関係ではないことを理解しているのだろう。 さらにいえば、両親だけでなく未央たち4人以外の誰も知らないこともある。 ――自分達は、魔法としか呼べないような力を操ることが出来る。 それは、未央たち4人だけなのか、それとも同じような変化を遂げた人もそうなのか、まだわからない。けれど、それが”異変”の一端であることは間違いない。 「ああもう、考えなきゃならない事が多すぎるよ……」 思わず弱気が口を突いて出る。 らしくない、と思いながらも、目じりから涙が伝うのを止められない。 「……っふ……」 視界がにじみ、嗚咽が零れると思った、その時。 RRRRRR…… 「……え……?」 不意に、携帯電話から小さな電子音が響いた。 お気に入りの着信メロディではなく、個人用に設定したその味もそっけない音は、確か…… 「……拓也?」 慌てて涙をぬぐい、ぱちんと画面を開いてメールを呼び出す。そこには、
たったそれだけの短いメッセージが並んでいた。 たった3行。たった30字の言葉。 けれど、それを見て未央はくすっと笑みを浮かべた。 「拓也らしいね。……うん。元気、でたよ」 きっと彼も同じような不安に襲われたのだろう。けれど、それを振り払い、こうして自分を励ましてくれている。 ならば、いつまでも自分がうじうじしているわけにはいかない。 「ええと、ありがとう、……これでよし、っと」 すぐにそれだけを返信し、ちょっと考えてから拓也がくれたようなメッセージを瞳と淳にも送りつける。 もしかしたらすでに拓也が同じメッセージを送っているかもしれないが、それならそれでいい。 送信を確認してから携帯を枕もとに放り投げ、未央はすっくと立ち上がった。 先ほどとは打って変わってすたすたと窓辺へ歩み寄り、シャッ!と勢い良くカーテンを開く。 眩しい日の光に目を細め、笑った。 「悩んでる暇なんか、ないよね。だってやることはいっぱいあるんだもの!」 そう言って、未央はさっと身を翻した。 まずは顔を洗い、着替えてから朝食の準備をする。病院にいた間に何があったのかをきちんと調べなくてはならないし、両親ともきちんと会話しなければ。 「――青い月と 赤い太陽、共にあって欠けないもの……」 口をついて出る唄が何かも知らぬまま、未央は微笑を浮かべていた。 あなたに潜む感情を 狂気も全てが現実で あなたの欠片であることを 先は真っ暗 闇の中 朝日の届かぬその場所で 希望へ向かって歩き出す 自分の道を 探すため…… |



Copyright(C) 2001- KASIMU all rights reserved.