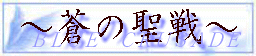
第三章 〜現れるもの〜
【2】
|
何度でも呼ぶよ 見つけられるまで―― それが何か、誰なのか、わかるときがこなくても 手に入れられるそのときを、ただ夢に見て お気に入りのスニーカーのひもをひっぱり、走っても解けないよう、入念に結び直す。 スカートのひだをなおしつつ靴のつま先を叩いてかかとを合わせながら、未央はくるりと回って心配そうな表情を浮かべている両親に視線を合わせた。 「じゃ、行ってくるね」 「本当に、大丈夫なの? まだ大人しくしていたほうが――」 「平気だって。あれだけ何度も検査して、もう大丈夫ってお墨付きも貰ったんだし」 玄関にかけられている鏡を覗き込み、大き目の帽子から日本人にはありえないレモンイエローの髪がはみ出ていないか、最後にもう一度チェックして。 最後に、度のゆるいメガネをかけて未央はもう一度にっこりと笑って見せた。 「ほら、これで目立たないでしょ? それに瞳ん家に行くだけなんだから、平気よ」 「ええ……そう、そうだけど――」 「……本当に、気をつけなさい。日が暮れる前に帰るんだよ。遅くなるようなら、電話しなさい」 「はーい。わかってるって……行って来ます!」 軽く手を振り、そう言って未央は軽い足取りで家を後にする。 心配そうな表情の中に、紛れも無い不安と戸惑いの色を浮かべた両親から、少しでも早く目をそらしたくて。 内心の想いを悟られることのないよう、あくまでもいつもと同じように駆け出した。 退院して、家に戻って。 ぎこちないながらもなんとか両親とのコミニュケーションをとった後、未央はかねてからの約束通り、親友の一人である瞳の家へと出かけた。 目的はかねてからの目標であった、魔法を使えるようにすること。そして家族や病院にいた人々がどうしても口を濁した、ここしばらくのうちにあった出来事、それらを調べること。 そのために、先に退院した未央と瞳、そして拓也は集まって話し合いをすることになっていた。 本当ならこういう話し合いなどには淳が欠かせないのだが、彼はまだ入院中。淳が退院するのはあと2,3日後だという話なので、とりあえず3人で少しでも話をしよう、と約束をしていたのだ。 それぞれの家族も未央たちを心配してはいたものの、やはり戸惑いのほうが大きい。 今はまだ、家族とは距離を置いたほうがいいということを無意識のうちに理解していたのかもしれない。 「おっ邪魔っしまーす! 拓也、もう来てるー?」 「いらっしゃ〜い。待ってたよ、未央ちゃん」 「おっせーぞ」 チャイムを鳴らし、慣れた様子でドアをくぐる未央に慣れ親しんだ声がかけられる。 明るい日差しが差し込むリビングには、すでに二人がのんびりと足をのばしてくつろいでいた。 透明なテーブルには、広げられただけのまっさらなノート。色とりどりのペン。放り出されたままの新聞と雑誌。ただつけられているだけのテレビには、ニュース番組が映っている。 いつもの定位置にさっさと座ると、入違いに瞳がすっと立ち上がった。 台所に向かいながら振り返り、 「お茶、あったかいのと冷たいのどっちがいい? あとコーラがあるけど」 「あ、ウーロン茶くれる? 冷たいの一気飲みしたいな、なんとなく」 「俺もおかわり、いいか?」 「はーい。じゃあボトルで持ってきたほうが早いね」 そう言ってキッチンに入っていく瞳の後姿、その緑に染まった黒髪を何とはなしに視界に収め、未央は目深にかぶっていた帽子を脱ぎ捨て、メガネを外しながら髪をかき回す。さらりとしたいつも通りの触感に、鮮やかな色の髪がふわふわと踊る。 小さな音量で流れつづけるニュースを不思議と静かな表情でただぼんやりと眺めていた拓也は、そんな未央の仕草に気付きつつも何も問わない。ただその小さな吐息に、レンガを思わせる赤茶色の髪の毛が揺れていた。 「おまたせー」 そのまま、静かな呼気だけが広がるリビングにほんわりとした微笑みを浮かべた瞳が入ってくる。 それにほっとしたような笑みを浮かべたのは、どちらなのか。 「ありがと、瞳」 「あ、俺食べ物持ってきてたんだ」 礼を言ってすぐにごくごくと喉を鳴らしてお茶を飲む未央の横で、そう言って拓也が取り出したのはコンビニの袋に入ったポテトチップスやポッキーなどの定番のお菓子。 足りない一人分の席をちらりと視界に移して、未央は目の前のテーブルに広げられたものを端に寄せる。拓也がテレビの音量を更に下げてからそれを手伝い、空いたスペースにグラスとお菓子が並べられた。 そうすると、自然とくつろいだ雰囲気が生まれ、どこかぎこちなさが感じられた空気も少しずつ消えていく。 最初に口を開いたのは、瞳だった。 「ね、お母さんたちと何か話せた?」 「ん〜。まぁ、少しはね。……拓也は?」 「まだ結構ぎこちない。なんか、とーさんたち変に気を使っててさ」 「ふぅん……瞳はどう?」 「あ、私はねぇ」 ほわり、と嬉しそうに瞳は深紅の瞳を細めて笑った。 幸せそうに、嬉しいと見ているほうにも感じさせるような笑みで、 「お父さんもお母さんも、凄く心配してくれて。最初は戸惑ったけど、やっぱり変わらないよ」 「……そっか。さすが、瞳のおじさんとおばさん」 瞳と同じように、どこかほのぼのとした雰囲気をもち、とても過保護でとても優しいあの両親なら、そうなのだろう。 それはとても、羨ましいことではあるけれど。 「うちはまだ、ぎこちないままかな……あ、そうだ。真吾のこと」 「ん? 真吾がどうしたって?」 昔からよく知っている、未央の弟の名前が出たことに拓也は首をかしげる。その横で、瞳も同じようにポッキーを口にしたまま目をきょとんと瞬く。 そんな二人を目にして、どう告げようかしばし迷い、 「あのね……真吾も、なんだって」 短く言って、自分の髪を軽く引っ張って見せる。 拓也も瞳も、「……そっか」小さく返事を返し、ちょっと困ったような、そんな表情で笑って見せた。 「俺んちは、俺以外は大丈夫だったよ。……あ、でも従兄弟がどうとか、言ってたかも」 「お隣の小学生の女の子、あの病院にいるって。朝、教えてもらったよ」 「……なんか、結構多いよね。変わったの。どうして、なのかな……」 「俺たちにわかったら、今ごろ頑張って研究してるお偉いさんたちがかわいそーだろ」 「それよりも、私たちにわかるはず、ないよ。淳くんならともかく」 「――瞳。それはあたしたちが馬鹿だっていいたいの?」 「え、違うの?」 ワザとらしく見える、けれどまぎれもない本気の言葉に、未央と拓也はがっくりと肩を落として「違う」と声を揃えた。きちんと否定しておかないと、瞳は時々事実を曲げて思い込むクセがある。 ……もしかしたら、完全に冗談のつもりで、ふたりをからかっているのかもしれないのだが。 そのまま、雑談とも愚痴とも付かぬことを延々と話しつづけ、昼食の時間もとうに過ぎ。 途中で注文したピザがすっかりなくなったころ、やっと未央たちは本来の目的を思い出した。 「そういえば、今日、これからのコトとかを話し合うために集まったんじゃなかったっけ?」 軽く首をかしげて瞳が言えば、ポテトの最後の一つを取り合っていた未央と拓也はぴたりと動きを止め、忘れてたとばかりに大きく目を見張って見せた。 「そういえば。……そのために瞳のうちに来たんだ――って、拓也! それ、あたしの!」 「よそ見したお前の負けだろ」 ポテトを飲み込み、意地悪く言って拓也はさっそくテーブルの上のゴミを片付け、用意しておいたノートと筆記用具を並べだした。 まっさらな、一度も使用した後の無いノートに3本のシャープペン、そしてやや使い込まれた後のあるケシゴムを手にして、拓也は二人に真面目な顔を向ける。 それにつられ、未央と瞳も同じように姿勢を正し、真面目な表情を浮かべる。 こくん、と喉を上下させ、拓也はゆっくりと口を開き―― 「で。……何するんだ?」 「……知らないよよーもー!」 「拓也くーん……」 未央はむきー、とレモンイエローの頭を抱えて起こり出し、瞳は力が抜けたかのようにふにゃ、とテーブルに頬をつけて頬を緩めた。 だってさぁ、と呟く拓也に、未央と瞳はそれぞれ顔を見合わせて深い溜息を零した。 「拓也くんて、普段はすごく真面目なのに……」 「ときどきどうしてこうなるのかなぁ……ね、わざとじゃないの、今の?」 「悪かったな、本気で忘れてたよ、どうせ!」 頬をうっすらと染めて起こり出す拓也に、自然二人はどこか冷ややかな視線を送る。 それでもせっかく本題に入ったところなので、とりあえずそのことは無視して未央はノートに手を伸ばした。もちろん、その際に深々と溜息をつくことはわすれないが。 「……言いたいことがあるならはっきい言え」 「はいはい、あとでね。……で、なんだっけ、魔法の訓練?」 「え〜と、あとね、これに書いてあるって」 ごそごそと、瞳はポケットから小さなメモを取り出した。 テーブルに載せたそのメモには、几帳面な文字でいくつかのことがらが書き並べてある。 「これ、淳の書いたメモか?」 「うん。この間、渡してくれてたの、忘れてたの」 「覚えててよね、瞳……で、何が書いてあるの?」 「ああ、えっと……やることそのいち、雑談ではなく話し合いをするように……?」 「……そのに。ノートを開くこと?」 「……俺たちは幼稚園児かよ」 眉をしかめて言う拓也だが、それを言った彼自身も、そして未央たちも淳が嫌味でそれを書いたのではないことはイヤと言うほどよくわかっている。 淳はごくごく真面目に、彼ら3人がやるべきこととして、それを書いているに過ぎないのだ。 とりあえず気を改め、その辺りの部分は除いて、必要と思われる部分にのみ、目を通していく。 「ええと、新聞からあの日以降に起きた、異常だと思われる事件を切り抜いてノートに張ること」 「無理をしない程度に、魔法の練習をしてみること。ただし、危ないことはしない」 「できるなら、自分達の周りでどれくらいの人が変化したのか、調べること……?」 「あ、瞳、最後のそれ、注意書きがついてるよ」 「え? ……あ、ほんとだ。これは4人そろってからやろう、だって」 「ふぅん? じゃ、とりあえず最初は簡単だな」 やり方まで詳しく書いてあったメモに若干情けなさを感じなくはなかったが、とりあえずいい案もないのだし、ということで3人は明日、それぞれの家族の許可を得た上で新聞の切り抜き、もしくはコピーを持ち寄ることを決めた。 これは3人の家庭でとっている新聞がそれぞれ違うこともあり、すんなりと決定する。 問題は、次のもの。 「この、『無理をしない程度に魔法の練習をしてみること』って……何をすればいいのかな?」 3人はそろって、頭を抱え込んでしまった。 何しろ、まず『魔法』という、それ自体がわからないのだ。以前にやってみたときはほとんど偶然とか反射的にとか、むしろ火事場の馬鹿力のようなもので。 病院で【光】を作ってみせた淳に話を聞き、その後なんども試してみたものの、誰一人として成功しなかった。 むきになって結局、何十回も試したものの、結局ただ疲れただけ、という散々な結果だった。 「……また、やってみる?」 「それはいいけどさ、淳が教えてくれた方法、間違ってるんじゃないか? 何回やってもダメだったろ」 「というか、あたしたちには合わないのかもね。別の方法じゃないと無理だとか」 「うーん。でも、とりあえずやってみるしかないでしょ?」 「そだね。じゃ、頑張ってみるか」 「だな」 頷き、3人はそれぞれ体を離し、リラックスした姿勢で椅子に腰掛け、目を閉じた。 自分達がかつてやった【炎】を呼ぶのは危ないしやり方がわからないので、淳がやってみせた【光】を呼ぶ方法を、淳の説明に従って試す。 閉ざした瞼の中の、明るい闇のなか、浮かぶのは彼の言葉。 ――まず、目を閉じて。片手に意識を集中して、そこに暖かな光が集まるように頭の中で想うんだ。 ――別に光じゃなくてもいいと思う。でも、たぶんそれが一番やりやすいと思うよ。 ――ゲームとかにあるように、呪文みたいに唱えてみてもいいかもしれない。その方が、ずっと何が出るかイメージしやすいだろう? ――信じて。僕は、みんなが魔法で僕を助けてくれたって聞いたから、やれたんだから。 ――だいじょうぶ。きっとできるから。 病院のベッドの上で、優しく言っていた淳の言葉を思い出す。 ふわりと、どこか淳の持つ優しさを感じさせたやわらかな光を。 その光が現れる前、感じたあたたかな流れを。 「――――ぁ」 つかんだ、と思った。 暖かな流れを。そこに至るまでの道を。その先にある、確かな力を。 何かを言葉にしようとして、未央はけれど、それが突然壊れるようにしぼんでいくのを感じた。 目を開けば、その手のひらにはなんの痕跡もない。見慣れた手のひらがあるだけ。 あとひとつ。なにかがまだ、たりていない。 そんな不確かな思いが胸を包み、未央は溜息を零すと時計に目をやった。 「意外と時間経ってるね。30分も頑張ってたみたい」 「瞳」 横からかけられた声に、未央は顔を向ける。 問い掛けるように首をかたむければ、瞳はちょっと笑ってダメ、と口を動かした。それに答えるように、未央もかるく手を振る。 わかっていたことなので落胆はない。ただすこし、残念だなと思うだけだ。 そして、二人はただひとり、何の反応もない拓也をそろって見つめた。 「…………」 拓也はひとり、ソファに座っていた。難しそうに眉間にしわをよせ、手首をぎゅっと掴んで。力を入れすぎてふるふると振るわせるその様子に、未央は思わず「ゴッドフィンガー!とか叫ばないかな」なんて思ってしまった。 瞳と二人でそんな拓也を見つめること、しばし。 やがて、拓也の眉間のしわがすこしずつ消えていく。震えるほどに握り締められていた手から力が抜け、そして『何か』が流れて――。 「…………」 「…………」 ごくん、と唾を飲み込んだのはどちらのほうか。 思わずふたり、手を握り締めあって期待に満ちた目で拓也を見つめていた。 淳を助けたいと願ったとき、たしかに繋がったもの。彼が見せてくれた柔らかな光が、あのときまとっていたもの。 その暖かさが、ここに、姿を現そうとしている。 拓也の、未央と瞳より大きな手のひらで『何か』が揺れる。 目に見えない何かが揺らぎ、そして 「ファイアー!!」 「ひゃぁっ!」 「わっ!?」 突然、目をかっと開いて渾身の気迫を込めて叫んだ拓也に未央と瞳は驚いて飛び上がった。 ドキドキと高鳴る胸を抑え、見たのは手を高々と上にあげて真面目そうな表情をしている拓也。 「…………」 「…………」 「…………」 瞳と手を取り合ったまま、言葉を口にしない拓也を無言で見詰め。 にやり、と拓也が笑みを浮かべた。 「どーだ、びっくりしただろ?」 「…………」 「…………」 「……ん? どした?」 はさみの形にした二本の指をかにのようにちょきちょきと動かしながら、固まったまま動かない未央と瞳を拓也は不思議そうに見つめた。 渾身のいたずらに対して、反応しない二人へのいぶかしげな表情。 拓也から感じられるのはただそれだけで、さきほど微かに見え隠れした『何か』は、もう微塵も感じられない。 それをたしかめ、二人は深い溜息を落とし、がっくりと肩を落とした。 「あーあ、あとちょっとだったのに……」 「拓也、さいてー」 「おいおい、なんなんだよ、いったい」 「……全然気付いてないし」 そうだろうとは思っていたが、やはり本人には欠片も自覚はないらしい。 すっかり気をそがれた未央はぷいとそっぽを向いて放り出されていたポッキーを口に入れた。 それを苦笑気味に見やり、瞳は不思議そうに首をかしげている拓也に向き直り、 「拓也くん、さっき魔法できそうだったんだよ。気付いてなかったでしょ」 「え? うそ、マジで!? ちくしょ、なんで言わないんだよ馬鹿未央!」 「ふざけて遊んだのは拓也でしょーもー。かっこよかったのにー」 「ホントだよね。絶対、あとちょっとで成功!だと思ったんだけど」 ちょっと困ったかのように言う瞳に、拓也は大げさにのけぞり、ばったりとソファに倒れ付した。 「うあー、失敗したー。すげーショック。俺もうだめだ、立ち直れない」 「あっそ。……あたしももう、やる気なくなっちゃった」 「そうだねー、ちょっと疲れたし……あとはまた、淳くんが帰ってきてからにする?」 「「そうする」」 同じタイミングで頷きを返す二人に、瞳はおっとりと微笑んでみせた。 いつもと変わらない、それが自分達の日常。 ――その、3人のすぐ横。 ソファの横に置いてある観葉植物のパキラの葉の端に、わずかに焦げたかのような跡があったのだが。 誰も気付くことはなく、そのまま忘れ去られていった。 波に浚われるように 私の手から零れてく―― 語りかける言葉が、流れる力を掴んで 現れるそのとき、わたしはきっと微笑むから ――第三章【3】へ続く |



Copyright(C) 2001- KASIMU all rights reserved.