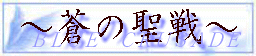
第一章 〜時の発端〜
【3】
すべてのものが 夢であるように―― それが真実であったから。 涙を隠し、ただ認めることを嫌った。 ふわふわ。ふわふわ。 空気の海を漂っているような感じがする。 光。闇。温かいの。冷たいの。頼りない感覚だけが、夢のあとを知らせてくれる。 (あれぇ? なに、してたんだっけ……?) わかるのは、夢を見ていたことだけ。 何か、大切な夢。忘れてはいけない、忘れてしまったこと。 たくさん、知りたいことがあった。 たくさん、知ったことがあった。 でも、ほとんど忘れてしまった。 覚えているのは、蒼い光と―― 「え?」 突然、何の前触れもなく目が覚めた少女の視界に映ったのは、真っ白い天井。幼いころに嗅いだ、薬品のツーンとした臭い。 (薬のにおい? じゃあ、……病院? 何で?) 横たわったまま、ぐるぐると思考だけが忙しく働いている。 何故病院にいるのかが判らない。自分はいつもと同じように学校から帰る途中だったはずなのに。それから先の記憶が途絶えているように感じるのだ。 「……とりあえず、起きよ」 確認するように声を出してから、肘を突いて起き上がる。ただそれだけの事に、酷く体力を使った気がする。 「ずっと前に盲腸で入院した時みたい……体が、動きにくい」 何故か腕に刺さっていた点滴のチューブをそっとはずす。その瞬間に微かに走った痛みに、顔を小さく顰める。 「いったぁ……なんで点滴してんの?」 赤くなっている個所を揉み解しながら、とりあえず辺りを見回す。 右――ベッドをはさんで壁。通路側のベットに寝ていたらしい。何かの機械を発見。 左――小さなデスクと椅子が並んでる。デスクには自分の鞄。隣の紙袋は制服だろうか。 前――カーテンがかかっている。気付かなかっただけでベットと周辺を囲んでいるらしい。 病院の大部屋らしい。カーテンがかかっているのでよく分からないけれど。もう一度見渡す。何か、変な違和感が…… 「……あたし、なんかヤバイ?」 カーテンのわずか手前に、ベッドを囲むように透明なビニールのシートが覆っている。何度かテレビで見たそれはたしか感染症とか、重度のアレルギー患者などに施されていて……。 (もしかしなくてもあたしって超ヤバイ? 冗談じゃなくて? しかも、なんかすっごく静かだし!) それまでぼんやりしていた思考がやっと回転しだしたようだ。まさか、新ての冗談で点滴まで打つはず無いし、こんなお金のかかることを平気でする知人はいない。 「やだやだ冗談じゃないよなにこれ!?」 ぱたぱたと無意味に手を振り、焦りを表現。 あたりを見渡すが、何も変化はなし。そこで唐突にぴた、と動きを止める。 「……とにかく、状況判断……だっけ? しないと」 テレビの見すぎであろう、あごに手を当てながらとりあえず落ち着くために格好をつけてみた。 いま出切る事――状況判断と、自分に異常が無いかのチェック。よし。まず身体に異常がないかのチェックをしよう。 彼女は自分の身体を入念に調べだした。 「足……痛いとこなし。腕……お腹……うん、みんなおっけー。体調は……ちょっとだるい。筋肉痛かも。なまってる感じ」 いちいち声に出して確認してから、その必要は無いのだと気付く。 まあいい。次は自分の記憶を確認しよう。 名前――榊未央。年齢は15なりたて。誕生日?……うん、覚えてる。 家族……4人。一軒家住まい。学校よし。……あとは? 最後の日。なにがあった? さわさわ、と揺れる風に髪をさらわれながら、ゆっくりと声に出して記憶をたどっていく。 金の風。眩く輝いているのはいったいあんなのだろう? 「朝。ご飯食べて学校へ行った。そんで勉強して――校長の長話聞いた。それからみんなとご飯食べた。午後……情報処理して……部活が早く終わって。雑誌を買おうとして走ってて、ちょっとかっこいいお兄さんにぶつかった。それで……それで……」 今度はあっさりと思い出せた。そんなに怖くも無い。光。フラッシュバックする色彩。意識が消えて――そして? 「……光が振ってきて、それで変な夢を――――っ!?」 ざあ、と一瞬で顔色が青く染まる。脂汗が滴り落ちるのを感じ、さらに嫌な予感が増す。 「か……か……鏡……たしか、鞄に……」 ぎこちなく手を伸ばし、何にも考えずにシートをめくって鞄を手に取る。きちんとシートを直すところに微妙に動揺が影響しているようだ。前ポケットから取り出した小さな鏡。流行嫌いの自分に母がくれた、1つ800円のやつ。目を瞑ったまま開く。 いきなり見つめる勇気は、無い。 大きく深呼吸をすること、数回。 「……よし」 まさに大害絶壁を飛び降りる気分で目を見開く。そして――ばふっとベットに逆戻りをしてしまう。鏡を握ったまま。 かつての自慢であった『金髪』が、柔らかく頬にかかる。 鏡に映っていたのは真っ青な顔色の、黄色に近い金髪と蒼い瞳を持った少女だった。 「……冗談じゃないよ……」 どうやら、しばらくは復帰できそうになかった……。 「……まあ、いいか。悩んでも仕方ないし」 そういって少女――未央が復帰したのは鏡を見てから10分ほどが経ってからだった。立ち直りが早いのが少女の自慢であった。あまり意味は無いし、落ち着きがないとか言われるけど。 「結構綺麗だし。さわいでどうこうなるものじゃないし。今はもっと重要なことがあるし」 とりあえず、目の色がもろにあの光と同じであったことはあえて無視することにした。着崩れした病院服を直し、髪を手櫛でといでからもう一度やり直す。 「……とりあえず、ここをでれば判るんだけど……」 それが最も手っ取り早いのだが、やはりこのシートを無視するわけにも行かない。いや、さっき無視したのは気にしないことにして。 問題は、どうやってここを出るか。そして、情報を得られるか。 「叫ぶ……わけにもいかないし。どうしよう……」 途方にくれながら溜息をつき、もう一度ベットに倒れこむ。そのまま頭上で腕を組もうとし……冷たくて硬いものが腕にあたった。 「これ、もしかして……」 それはもちろん、ナースコールと呼ばれるものだった。じっとそれを見つめた後、おもむろに少女はそれを押した。 えい。ぽちっとな。 1階、ナースセンターにて。 「あら? 誰かコールしてるわよ、3階で」 「301号室の山田さんかしら? またあのおじぃちゃんは……」 「ええと……ちょ、ちょっと! これ、あの患者さんじゃない!?」 「え?――ほ、本当! はやく先生に連絡を! ご家族も来てたでしょ!? 放送を!」 穏やかな雰囲気に包まれていたナースセンターは、突如として慌しくなった。 その当の本人は部屋でのんきに欠伸をしていたのだけど。 「う〜ん、ちゃんと伝わったかな……」 ベットに寝転んだまま、あくびをしたちょうどその時外から何かが走ってくる振動が伝わってきた。 ドタドタドタドタ……バタン! シャアァァァァ!!! 「未央!!!!!」 「榊さん!!!」 「あ、やっほ〜母さん♪」 飛び込んできた女性と、医者らしき人物に向かって未央はにこにこと笑いかけながら両手を『にぎにぎ』として見せた。テレビで覚えた新・必殺あいさつ技。その名も…… 「お、っは〜♪」 本人に自覚は無かったが、彼女を心から心配していたこの二人はこのあいさつで腰が砕けた。がく、とひざの力が抜けてそのまま床に座り込む。 そんなこと予想もしていなかった未央は目をぱちくりと瞬かせた。 「あれ? どしたの?」 「ど……そうしたのって……未央、あなた大丈夫なの?」 「うん、全然元気だけど?」 「……と、とにかく……検診しましょう」 よろよろと立ち上がったのは青年をやっと越えたほどの男性。なかなか優しそうで「べりぐっ」だ。聴診器を首にかけてはいるが、あまり使ってないように見えた。 彼はしばしためらってからシートの内側に入り、少女に近寄った。 「はじめまして。僕の名は浜口です。君の……君達の担当医のひとりだ。さ、手を出して」 「あ、はい。……あの、君達って?」 手を取って脈を計りながら、後からやってきた看護婦に何かを指示する医師の顔が歪む。まるで、何かを失言したようだ。だが、何を? 「質問はあとにしよう。……脈は正常。瞳孔も異常なし。体調はどうだい?」 「ちょっとだるくて、筋肉痛みたいです。あとは平気。……あの」 「後でといっただろう? ……熱はなし。まったくの健康体といってもいい。問題があるとすれば……」 きゅるるるる〜、と言葉の終わりとともに小さく響く音に、未央は顔を赤らめた。 くす、と聴診器をしまいながら医師が笑を零す。 「5日寝たきりだったから、お腹がすいただろう。でもまだ点滴だけどね」 そばに置いてあった機械を確認し、「……脳波に異常なし、か」小さく呟いてからデータを写す。点滴を再びつけ、反対の手と胸の辺りに何かを取り付ける。吸盤のようになっているもの。いつかの心電図をとったときの感じに、ちょっとだけ似ていた。 「……よし。あとで精密検査を受けてもらうよ。……すみませんが、まだこのシートは外せないので気をつけてください。それと、あまり近付き過ぎないようにして下さい」 後半は少女の母親に向けての台詞。だが、少女はそんなこと聞いてはいなかった。さっき彼が漏らした言葉。いったい、どういうことだろう? 「では、他の仕事が出来ましたので……要があればナースを捕まえるか、ナースコールをして下さい」 「はい。どうもありがとうございました」 「……あの!」 「また後で。もう少ししたら精密検査するよ。異常がなければシートも外せるし、ご飯も食べれる。質問はその後で聞こう。それまで我慢してくれ」 「ちょ、ちょっと……!」 言うだけいうと彼はさっさと立ち去ってしまった。 (なにかを隠してる? なにを? 何のために?) 母親は安堵したような表情で娘を振り返る。 「心配したのよ、未央。眠ったままだし……とにかく、無事でよかったわ」 「うん……。ね、あれから何日たったの?」 「え?」 「あたしが学校に行って、……何日がたったの?」 静かな表情で問い掛ける娘に、彼女は溜息をついて答えた。 本来なら、知らないで欲しいのだけれど…… 「……5日よ。あなたはあれから丸5日眠っていたの。それ以上の事は答えられない」 「……そう……。5日、か……」 ふ、と俯く。何故こんなに長い時間眠っていたのだろう? あの夢と、変質した髪を瞳と何か関係あるのだろうか? いや、ないとおかしい。すべて関連しているに決まっている。 では、どういうことなのだろう? 何故、色が変わるなんてことがあった? 少女の自問は突然の物音で遮られた。 「は〜い、榊さん検査しますよー。お母さんは離れていてくださいね。さ、これにのってくださーい」 間延びした看護婦の声にしぶしぶ移動する。 (あたしはどこもおかしくなんてないのに……) もちろん、それは検査する誰もが思うことだったのだけど。 検査が終わるまで、結局丸一日がかかってしまった。 何故だかわからないけど、自分がおきたことで病院は特に忙しくなったらしい。 同じ部屋のベットにはカーテンが引かれていて中の様子が確かめられない。母親は面会時間が終わったとかで名残惜しそうにしながらも帰っていった。 「はぁ……あたしもごはん食べたいなぁ……」 検査の結果が出るのは明日。異常がない場合に限り、このシートを外せるといった。しかし、必ずしもそうなるとは思っていなかった。 (原因不明で丸5日寝込み、髪と瞳の色が変わるなんて異常だし。そうそう退院とか、できることはないだろうなぁ……お腹すいたし) 夕食は当然なし。ただ、特別に飴玉を一個貰ったので大切になめている。腹のたしになるわけではないが、気はまぎれるからだ。 時計は10時を指している。消灯時間は過ぎ、とっくに電気は消えている。廊下を時々ナースが通っていく。足音を忍ばせてい入るが、たくさんの人が通っていく。それも、忙しそうに、早歩きで。時には走っていくものもある。 「……あたしが起きて、何が変わるんだろう……」 あの夢の暗示。ほとんど忘れてしまったけど、何か大切なことを言われたことは覚えている。何かを、選び取れといわれた――そんな気がする。 「……寝て、明日また聞こう。今考えたって無駄だから……」 拭えない不安。 忘れてしまったことで、何か大切なことがあったはずなのに。 (寝たら、またあの夢を見れるかもしれない……) ちいさな希望を胸に、少女は眠りについた。 そして、しばらくの後彼女は仲間に出会うことになる。 大切な仲間に。これからの時間の殆どを共にする、親友達に――。 大切な貴方へと 送る筈だった言葉を―― 届く事の無い、願い。 でもそれは確かな『想い』であり、『願い』だから。 いつかきっと、それを現実にするために。 |



Copyright(C) 2001- KASIMU all rights reserved.