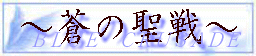
第一章 〜時の発端〜
【4】
数え切れないざわめきの中 自分を抱き締め怯えてた―― それが果てしないモノだと、何処かで理解していたから。 震えるように、身体を抱きしめていた。 少女――未央が目覚めてから、すでに3日が経とうとしていた。今は実質4日目にあたる。 あれからという物、検査ばかりで外出の許可もない。 昨日からやっと食事がもらえるようにもなったが、あまり楽しくもない。ずっと点滴だったからといって、『ならし』で冷めたおじやしか食べていないのだ。 明日にはもう少しまともなものがでる、とは言ってもたいしてかわらないだろう。最近は病院食も良くなったとはいえ、こういうメニューではなんの代わりも無い。 救いといえばこっそりと母の鞄からくすねたキャンデーだけ。新発売の『はにー・れもん&ぱいん』味。なかなか美味しいが、数が少ないのであまり食べられないのが難点といえる。 看護婦さんに頼み込んで買ってもらった週刊誌も、もう幾度となく読み返して飽きた。 CDを持ってきてもらったが、それもそろそろ聞き飽きて歌詞も覚えてしまった。新しいCDが欲しいが、母は用事とかで明日まで来れないらしい。 今の状況を一言でいうと、 ――暇。それにつきる。 「……そろそろ脱走するかな……」 などどいう物騒な言葉が口を突いて出るようにもなってきていた。 時間感覚がなくなりかけているので時刻は時計を見て確認するようにしていた。 現在は10時30分。そろそろ検診や昼食の準備などで忙しくなりだす時間だ。 「だいたいさ。何があったのか聞こうとしても誰も教えてくれないし? あの先生だってほとんど顔見てないし。検査がすぐに終わるとか言って、2日もかかってさ。それで結果待ちでさらに時間がかかるってどーいうことよ? まったく、これだから市立病院は……」 無意識に金色――黄色に変質した髪を触っている事に気がつき、嘆息する。 さらさらの髪は冷たくて気持ちいい。 でも、目に見える色があまりに以前と違いすぎて、面会に来た両親はすごく戸惑っていた。 母親はそんなでもなかったが、父親は明らかに動揺し、それを悟られないように涙ぐましい努力をしていた。そんな姿を見せれば返って傷つくということにも考えつかずに。 それに、あって然るべきの動揺や違和感がまったく感じられなかったのだ。 まるでこれが自然な、もとの姿であるかのように当然だと感じた。そんな自分にこそ、違和感を感じた。 「なんでかわったんだろう…校則違反になっちゃう。まあ、レモンイエローで綺麗だけど。それに、この瞳の色」 まざまざと甦る、光。熱いとも寒いとも感じた、不思議な感覚。一瞬だけの夢。 自分の瞳を見ると、どうしてもあの『光』を思い出してしまう。するとどうしようもなく身体が震えだしてしまう。だから、なるべく考えないようにはしていた。 一種の現実逃避だとは思う。でも、さすがに自分の瞳の色があの『光』とまったく同じで、そしてあの『夢』のことを考えればどうしても関連があるのではないかと考えてしまう。 それはいやだ。自分は何もない、普通の女の子なのだから。そう、思っていたいから。 よく『肝が座っている』とか『勇気がある』とかいわれる彼女でも、さすがにこの事実を自分ひとりで受け入れる勇気はなかった。 もちろん、こんな現象が自分ひとりのものだとは思っていない。 かすかな夢の断片に、たくさんの人がいたのを覚えている。おそらく、もっとたくさんの人が自分と同じ目にあっているのだろう。目覚めているかは判らないけれど――。 おそらく、このカーテンの向こう側、同じ部屋の残る5つのベットの主も同じハズ。 一日に何度もカーテン越しに見舞いの客がくるのが見える。彼らはそのまま、カーテンの中に入って何かを話し掛け、時には叫び――そして、あきらめて帰っていく。 別の病室から叫びが聞こえ、そして看護士や看護婦たちの大騒ぎとなるのも、一度や二度ではなかった。 「もしかして、みんな寝てるのかな……あたしみたいに」 昏々と眠りつづける人々。彼らは一様に変化してしまっている。それが何を意味するのかもわからない。もしかしたら、二度と目覚めないかもしれない。 何があったのかも判らないまま、変わり果てた姿で眠り続ける家族、恋人、友人。 それを見ているのは辛い。――その結果が、あの叫び声なのだろう。 涙と共にあふれ出す想いが、言葉となって溢れ出す。 「だとしたら……悲しいな。でも、あたしも目覚めたんだから――きっと、みんな起きるよね」 きっと、きっと――そう何度も呟きながら、小さな窓から見える空を見上げる。 前に本で読んだことがある。昏睡状態――植物状態の人間が目覚める確率は、日を追うごとに少なくなっていくと。 日に日に大きくなる不安。唯一の希望が、彼女なのだ。 やっとそれに思い当たり、未央は複雑な表情になる。 なぜ彼女が目覚めたのか――それを調べれば何かがわかるかもしれない。 だからこその、この検査。そして拘束されている事実。それを思うと迂闊にも逃げられない。 「……どうしたらいいんだろう。みんなが一斉にパーッと起きれば関係ないのに……」 「はーい、榊さん、昼食ですよ〜」 そこまで考えた所で、看護婦が少々早めの昼食を持ってくる。 メニューはやはりおじやかと思いきや、ちょっとレベルアップしておかゆだった。 おしんこがセットになっている。そしてあつ〜いお茶がちょっといい感じだ。 それを文句をいいつつも堪能しているうちに、生来お調子者でもある彼女は悩んでいた事をすっきりと忘れてしまった。 「……うううむむむむぅぅぅぅ。ああ、よっくねたぁ〜☆」 大きな欠伸をしつつ未央が未央を起こす。結局、昼食を食べた後に寝入ってしまい、時間は2時を過ぎてしまった。 「起きると暇なんだよねぇ。どうしようか……」 しばし考えるが、もちろんいい案などない。数分考え、出た結果は彼女らしい物だった。 まずは身体中につけられた小さなパッチと身体に巻きついたチューブなどをさっと外す。 くしゃくしゃになった髪を整え、さっと緑地のパジャマを脱いで着替え用の白いT−シャツと短パンに履き替える。シャツは赤いワンポイント文字が結構気に入っている。短パンは確かバーゲンで買って貰ったもので、ジーンズ生地が気持ち良い。 その日本人として決してありえない色の髪と瞳を別にすれば、何処から見ても見舞い客にしか見えない。そして元気のよい彼女の事、どう間違っても患者には見えないからだ。 この間学校に行ったときに持っていっていた、すっぽりと被る形の帽子を鞄から取り出す。 それを深く被り、時々かけている眼鏡をつけて目の色を誤魔化す。 幸い、蒼は目立ち難い。赤とかならすぐにわかるだろうが、眼鏡をかけた以上そう簡単にはわからないはずだ。 帽子を被り、眼鏡をかけて髪の色を隠した彼女はもはや普通の人と何も代わらなくなった。 もっとも、病院の中で帽子を深く被ったその姿は異様と言えるものがあったが……。 「さーてとっ。もうこのシートを外してもいい事は知ってんだからね〜♪」 医師たちの会話を思い出しながら彼女はカーテンごとそれをくぐり、静かに扉を開く。 きょろきょろとあたりに人がいないのを確認し、さっと小走りにかけて階段へ向かう。 外来患者も使うそこからなら、絶対に正体がばれる事は無いだろうと踏んでの事だ。 「さぁ〜って☆ まずは、この階の探検からしよーっと!」 きらきらと好奇心に輝いた瞳で、少女は歩き出した。 <――では引き続き救助が続いていますがどこも異常事態に対処できず、混乱は広まるばかりとなっています。自衛隊が出動し、市民の避難を促している地域も少なくはなく――> 彼女の通り過ぎたすぐ側で、全国放送のテレビが流れていたが彼女は気付かなかった。 おそらく、そのほうが良かっただろう。 ――今は、まだ心の準備が出来ていないのだから。 市立であるこの病院はそれなりの大きさと広さがあり、歩いて回るだけでもそれなりに時間がかかる。未央がもといた部屋を中心と考えて、とりあえず左方向へと歩き出した。 要所要所いる看護の者たちと直接出会わないように気をつけ、それでいて堂々と歩く。 右手側にある病室の名札には、常にその部屋の許容人数と同じだけの名前が書かれていた。 その中で自分の知り合いと同じ名前をいくつか見つけるうち、どんどん不安が溢れてくる。 (……なんかやぁ〜な、感じがする……) いくつめの部屋だろうか。今までの6人部屋から、1人部屋へとフロアがかわる場所に辿り着いた。人気も少なく、ひんやりとした空気が漂っている。 「ふえ〜。そっちはお金もちがいるような場所かな……。さっさと戻――」 ふと視線を上げた先に、この階最後の6人部屋に2人の名前がある。 一人は女の、もう一人は男の名前だ。その名前に見覚えがあるような――。 どちらもありふれた物だが、やはりこういうときの偶然は少ないだろう。 「……まさか、ねぇ? 二人に限って……でも、ないともいいきれないし……」 油汗が流れる経験なんて初めてだと頭のどこか一部分で考えながら、未央は結構長い間そこに立ちすくんでいた。ただ立っていても仕方ないと思い震える手でそっと扉を押す。 ――ガタッ。 「あ、違う! 横だった」 動揺のあまり初歩的な間違いをし、もう一度呼吸を整えてから扉を開く。 今度はすんなりと開く。中に人がいないのを確認し、そっと身を隠すようにして素早く中に入り、扉を閉めた。 心臓がうるさいほど高鳴っている。かつて無いほどに緊張しているのがわかる。 6つのベットが並ぶ中、2つを残して全てが空になっている。 残りの二つのベッドは彼女自身がいたところと同じ様に、シートとカーテンで隠されている。 ちょうど二つとも横に並んで使われている。カーテンやシートがなければ、横を向いておしゃべりができる位置だ。きっとつまらない入院生活が楽しくなるだろう。 ――その本人が起きていれば、の話だが。 「これはもう、見るしかないよね……よし!」 ぐっと力強く両手を握り締めると、眼鏡と帽子を外してポケットにつっこむ。 そろそろと足を忍ばせ、両方のベッドの間に入る。そして、カーテン越しに中のシートもぎゅっと掴みとる。 (……さん……に……いち……) 目を瞑ったままでカウントダウン。それがゼロになった瞬間に、さっとそれらを開く。 ドクン、ドクン、と大きく波打つ心臓。もしかしたら音が外に漏れているのではないかと思うほど大きいと感じる。 「…………」 目を開いた未央は、その場に座り込んでしまった。ひざの力が完全に抜けている。 まさか、という思いとやっぱり、という思いがめまぐるしく脳裏を駆け巡る。 こめかみのあたりががんがんする。凄い勢いで血が流れているのだろう。 ただ、視線だけは動かない。やがて、ゆっくりと顔を動かしてもう一つのベッドにも目を向ける。 (なんで……どうして……) 赤茶色の髪をした少年。ハンサムというわけではないけれど、どこか魅力を感じる顔立ち。 緑味のかかった黒髪の少女。長い髪がその顔のまわりに緩やかなウェーブを描いて流れている。 「……瞳……拓也……」 仲の良い友人たちの寝顔を見つめ、未央はただ呆然と座り込んでいた。 勇気などいらない ただ震える心を抱き締めて あるかどうかもわからない 希望だけを信じつづけて―― 諦めたら、終わりだから。 まだ、始まってもいないのだから。 これから起こる筈の、『奇跡』を信じて……。 |



Copyright(C) 2001- KASIMU all rights reserved.