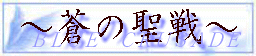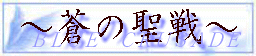青い月と 赤い太陽
共にあって欠けないもの
空に光が駆る時
月の魔法が動き出す
さらり、と小さな窓につけられたカーテンが静かな音を立てて揺れる。
窓枠を滑り、微かな絹擦れの音だけを立ててそっと風になびき、小さく絶え間なく揺らめく。
海の波のように、緩やかに……眠りにつく幼子を、目覚めさせないかのように。
優しげな真昼の太陽の光がさして広くもない部屋に射し、明るい色を少しずつ零していく。
ベッドを囲んでいる淡いパステルグリーンの色をした薄い布地のカーテンは見事その役目を
果たし、中の様子をしっかりと隠している。その中に見えるのは微かな影のみ。
そして、そのカーテンの中にある小さなベットに“彼”は眠っていた。
パイプで作られた病院のベッド、その白いシーツに横たわった彼の体は驚くほど華奢な輪郭を
毛布の上からでさえ描き、流れる風に揺られた前髪は額を流れ、その瞳を柔らかく覆い隠す。
端整な顔立ちをしたその少年は、瞳を閉ざしたまま緩やかな呼吸を繰り返していた。ゆっくりと
上下する胸。トクトクと緩やかに動き続ける心臓。それらが彼が生きている証かのよう。
横たわり深い眠りに落たまま、ピクリともせず――彼は眠り続けていた。
まるで、何かを待っているかのように。
――さぁっ……
再び風が流れ、カーテンを揺らし少年の髪をも揺らしていく。それは寒さを与える
ものでなく、むしろ心地よい暖かさを生ある全てのものに与えていく風。若葉と水と――さまざまな
命のにおいをいっぱいに詰め込んだ、優しい風。
さらさらと涼やかな音をたて、少し長めの髪が零れ落ちてベッドのシーツへと散らばっていく。
少年の、美しい――輝く月の雫のような光沢を持った、青銀の髪が。
青い光に導かれ
妖精たちが降りてくる
お腹をすかせた魔物達
歪なダンスを踊りましょう
明るく光る宝石と
冷たく光る剣を持ち
先へと向かって走り出す
「おっはよ〜!」
「未央ちゃん! おっはよう〜」
「お、やっと来たか……はよ」
朝と言うには少々遅く、昼というにはまだ早い時間。
とある病院の一室で、未央はドアを開け放つと同時に元気いっぱいの声と共にとびきりの笑顔を
浮かべる。それに答えるように、中にいた二人もにこやかな笑顔と共に彼女を振り返った。
ぱたぱた、と赤い安物のスリッパをひっかけた素足で黄金色――レモンイエローに近い金の髪を
した少女は駆け出す。ひらり、と青い布地のT-シャツと真新しいジーンズがなびく。
向かう先には、同様にスリッパをひっかけた普段着姿の少年と少女の姿。
未央は嬉しさを隠し切れないかのような笑顔を浮かべ、口開く。
「ね、聞いた? あたし達もうすぐ退院しても良いって!」
「そんなのもう知ってるって。俺達も今、それを話してたんだ」
「え〜? じゃあ何であたしを呼んでくれなかったの?」
「だって、未央ちゃんなら何も言わなくてもここに来ると思ったんだもの」
ぷぅ、と頬を膨らませる未央に、瞳はベッドに腰掛けたまま――ここは彼女に、と宛がわれて
いる個人用の病室なのだ――当然のように胸を張る。
ベッドの側に置いた椅子に座っていた拓也も、同じ様な表情を浮かべている。
「それに、誰かさんは朝寝坊してたみたいだしなぁ?」
瞳の言葉尻に乗るかのように告げる拓也に、未央はバツが悪そうな表情をして髪を片手で
いじる。その本物の金に輝く稲穂の色をした髪は、きらきらと陽光を反射して眩しいほど。
拓也と瞳はその輝きの美しさに、僅かに目を細めた。
自分でも、寝坊したという事はわかっているのだ。より正確に言えば、朝目覚めて朝食を取った
後に二度寝をしてしまい、この部屋に来るのが遅くなったのだ。
拓也は起きて朝食を食べた後監視役の者から退院の知らせを聞いてすぐにここに来たし、瞳に
いたってはここが彼女の部屋なのだから遅れようがない。
3人共またこの部屋に集まってきたが、別段昨夜またここに、と話したわけではない。ただ
ごく普通に、当然のごとく集まったのだ。
瞳は2人がここに来ると当たり前のように思っていたし、2人も瞳はここにおり、自分もここに
来るべきだと疑いもしなかった。
3人ともが、それぞれの行動を正しく理解しているのだ。自分達の役割というものを。
「まぁ、昨日夜更かししちゃったからちょっと眠くて遅れたのは確かだけど……」
「確かだけど、じゃないだろ。――んで、どう思う?」
口篭もりながら言い訳する未央を冷たく見やった拓也はすぐに表情を切り替え、心なしか
落ち込んだかのように肩を落とした少女に尋ねる。
その表情も、口調もさっきとは違いやや厳しく緊張した物へと変わっている。
それを敏感に感じ取り、未央はじっと目の前の少年の瞳を覗き込んだ。何度見ても見慣れない、
その深い緑色を湛えた不思議な瞳はいつになく彼の想いを現しているかのように見える。
「どう、って?」
「さっきから二人で話してたの。なんで……こんな突然に突然退院の許可が下りたんだろうって」
足を折り曲げ、ベッドの真ん中で膝を抱えた瞳が呟くように言う。漆黒に緑色を混ぜたかの
ような色に染まった彼女の髪は、いつも通りに頭の後ろで高く結わえられていた。
きし、と僅かにベッドが軋む。真っ白なシーツをくしゃ、と片手で握り締める手。
立ったままだった未央はそんな彼女の隣にそっと腰掛けた。また、ベッドが軋んだ音を立てた。
「だって、そうでしょ? 昨日まであんなに検査とかされて、変な監視の人までつけられてたのに
……それなのに、突然退院して良いなんて。おかしすぎるでしょ?」
「俺たち、意外と重要人物なんじゃないか? 俺達が思ってるよりも、ずっと。なのに」
思い浮かぶのは、目覚めてからの事。
執拗なまでの検査。その繰り返し。医師たちの、看護婦達の視線。
目覚めた時、彼らのベッドを取り囲んでいたのは何だった?
自分達の体に、腕に取り付けられていたチューブは、何のため?
「あたし、……最初は何かの病気になったのかと思った。起きた時、周りをビニールのシートが
囲んでて……腕には点滴のチューブが刺さってて。こんなの、どう考えても普通じゃない。でも、
検査を受けたらシートは外された。親にも会えた」
二人を見つめる、その眼差し。そこに含まれる、微かな恐怖。
それに2人は気付いたのか。気づく事が出来たのか。
「どうして? なんでそんな処置がしてあったの? それに、もしあたしが何らかの病気に
懸かっていたのなら、何故そんなに早くシートは外されて、両親とも会えたんだろう」
「……俺達が目覚めたすぐあと、"アレ"が現れた。んで、……"アレ"は消えて、さ。そしたら
また監視付きの隔離。……なのに今日起きてみれば、“監視係り”のオバサンが朝食を持ってきて
『退院許可が下りました』って。……一体、どういうことなんだよ」
苛立たしげに言う拓也。不満げに尖らした唇が、はぁ、と溜息を零す。
やや硬質の赤茶色の髪を右手でくしゃりとかき混ぜ、横目で未央をじっと見つめる。
「……わからない事だらけだ。それに、退院の許可は降りたけどそれがいつかは知らされてない」
「何度聞いても、教えてもらえないの。かわりに、院内は自由に行き来していいって。午後には
親とも面会していいって……それしか教えてくれないし、他の病室は絶対に入っちゃ駄目だって」
「未央が来る前に、二人で売店に行ったんだ。お金は元々持ってたのがあったし……それで
二人で新聞を買おうとしたら、新聞はここ数日発行されてません、だと」
「発行されてない?」
未央は不思議そうに首をかしげる。それはまたおかしな話だ。
柔らかな音をたて、瞳はベッドに身を横たわらせた。腕を投げ出し、視線はどことも知れぬ
方を向いている。美しく豊かな髪が、ふわりと辺りに広がる。
さらさらと流れる、音。
「それに、私たちはテレビを見ちゃ駄目なんだって。談話室とかに行ってもすぐに看護婦さん
とかが来て、テレビの調子が悪いので見ないで下さい、って言うの」
「……何かを、隠そうとしてる……って事?」
「さぁな。新聞が発行されてないってのは確からしいけど」
俯く拓也。視線を合わそうとしない瞳。
そんな二人を見て、未央は僅かに胸がうずくのを感じた。
そうだ。考えてみれば当然の事。立った一晩で、不安が消える筈が無い。むしろ、小さな不安が
胸の中で膨れ上がる。誰だって、こんな目に会えばそうなるだろう。
自分の胸の中にある、この理由のわからない恐怖が、未だ消える事の無いように。
「……ね、雑誌も売ってなかったの?」
「ああ。一部を除いて、週刊誌とかは全滅。テレビも駄目、ラジオも駄目。携帯はとられてるし、
俺たちはどうしたって……何があったのか、調べられないんだ」
「え? 携帯がとられてる?」
ざ、と顔を青くした未央を面白そうに見やり、拓也は小さく笑みを浮かべた。
変わらない。どんなことになっても、彼女はいつも通りでいてくれる。
だから、自分もなんとかなっているのだろう……それを、彼女が知ることは無いが。
「昨夜カバンを調べて気付いたんだよ。聞いてみたら、ここは携帯とかが禁止だからナース
センターで預かってるってさ。プライバシーの侵害だっての」
「退院するときはちゃんと帰してくれるって言ってたよ」
くすくす、とこちらも笑い声を零す瞳に安堵の表情を浮かべる未央。それが可笑しくて、
二人は更に笑みを深くする。
――大丈夫。みんなと一緒だから。一人じゃないから。
「え、え、なんで笑うの? ね、何で? あたしそんな変な事言った?」
「べ、別に……そういうわけじゃ、ないけど……ぷっ」
口を手で抑え、精一杯に声を小さくしながらしかしその笑みを隠す事は出来ない。
先ほどまでの雰囲気はどこへやら、小さな病室に楽しげな笑いが溢れている。
笑い続ける二人に、起こったような表情をしていた未央も次第につられるように笑みを浮かべ、
いつしか声を上げて笑う。
昨日言ったばかりじゃない。暗い事ばかり考えない方がいいと。楽しい事を考えていた方が
ずっとずっといいに決まってる。
目じりに浮かんだ涙をぬぐい、瞳は身を起こした。
「ねえ、あとで電話しようよ! 電話ならいいだろうし、父さんたちとも話したいし」
「そうだな。どうせ時間は有り余ってるんだし、さっさと見舞いにこーい! って発破をかける
のも楽しそうだしな」
「あ、それよりももう一度探検しようよ、ここ。まだ行ってない場所もあるし、もしかしたら
本当に“アイツ”もいるかもよ?」
「よ〜し、じゃまずは探検! その次に電話! んでなんか美味しい食べ物、買ってこようぜ!」
「さんせ〜!」
「じゃあ、行こ! ほらほら早く!」
ぱっとベッドから飛び降り、瞳が駆け出す。
その後を追うようにして拓也がゆき、未央が立ち上がる。
わからないのなら、これから少しずつ調べればいい。
ただじっとしているだけでは、何もわからないのだから。
財布をポケットに、勇気を左手恐怖を右手に彼らは駆けだす。
彼らは探しているのだ。彼を。最後の友を。運命に必要な仲間を。
決して、それを意識しているわけでなく。
それは、ただ必然であったから――。
明るく光る宝石と
冷たく光る剣を持ち
先へと向かって走り出す
でも 忘れてはいけないよ
あなたに潜む感情を
狂気も全てが現実で
あなたの欠片であることを