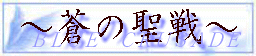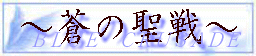3人は結局、お昼ご飯を棒に振る覚悟で溢れんばかりの好奇心を満たす事にした。
確かにお腹はすくし怒られるのはイヤだが、それよりも今はもっと気になる事があるのだ。
退屈なばかりのこんな病院の中で、こんな刺激的な出来事を見てみぬフリなどしたらもったいない
ではないか。
好奇心旺盛な彼らは、そんな無邪気な意志のもとに行動を起こしていた。
それに、その病室へと向うのは思いの他簡単だった事もある。
大きな声を出しながら走っていく医師や看護士を追いかけて歩いていけば、自ずとそこへと
たどり着くのだ。わざわざ探すまでも無かった。
「ここ、かなぁ?」
開け放たれたドアの少し手前で、彼ら3人は立ち止まった。
首を長くして中を覗くようにして、瞳が後ろに立つ拓也達に尋ねる。
後ろを振り返っていた拓也にかわり、未央が瞳の横に首を覗かせる恰好になりながら答える。
拓也はそんな2人に気がつきながらも、辺りをきょろきょろと見渡している。
「多分ね。さっき、前を走ってたお医者さんが入っていったでしょ?」
「……お、ここって6人部屋だ。でも8人くらいいる……ほら、名札が8つある」
「ほんと。でも、どれも読みにくい字で書いてあるね。なんか達筆すぎるんじゃない? ねぇ瞳、
これ読める?」
「ん〜……わかんない」
困惑したような表情で首をかしげる瞳。それを2人も困惑したように顔を見合わせた。
そこへ。
「ちょっと、あなたたちどいてっ! 邪魔よ!」
「わ、ごめんなさいっ!」
いくつかの薬のパックやビンを抱えた看護婦に押しのけられ、未央は思わずといったように
反射的に首を竦め、謝罪する。拓也たちも共にさっと通路の端へと移動する。
しかし30代とみえる看護婦はそんな彼らを全く見向きもせず、まっすぐに病室に飛び込むと
奥にあるベッドへと駆け寄っていく。
一番左奥にあるベッド以外は全てカーテンが引かれている。そこにいるものたちはみな、おそらく
まだ“目覚めていない”のだろう。
直感的に、未央は――未央達はそう思った。それがわかった。
そして唯一開かれているベッドはしかし、数人の医師や看護婦の体で遮られて見ることが叶わない。
(……あれは……?)
3人でドアにしがみ付き、中の様子を窺おうとするが動き回る人の体で全くと言っていいほど
様子を見ることが出来ない。
見ているだけでも、彼らの切羽詰っている様子は手にわかる。本来ならさっさとこの場から離れ、
邪魔をしないほうがいいのだが……。
しかし、どうしてか気になってこの場から離れる事ができない。
軽く顔を見合わせ、3人共が同じ感情を抱いている事に軽い疑問を感じながらも彼らは再びこの
病室をそっと覗きこんだ。
その合い間にも、医師たちは忙しく動き回って何かの薬を与えたり大きな機械を作動させたり
している。それは、時々ドラマなどでみかける“生命維持装置”とやらになんとなく似ているような
気がした。
不吉な、予感。
胸の中で、何かもやもやしたものが大きくなっているのがわかる。
「追加ですっ!」
「早く投与をっ! 点滴繋いで! ――くそっ、家族に連絡は!?」
「しました! でも、誰もいなくて……」
「……とにかく、出来るだけの事をするしかない。――君、彼の名前を呼んで!」
「はい! 小松君、小松君! 目を開けて! 小松君!」
医師の指示に従って一人の看護婦が呼びかけたその名前に、ピクンと彼らは大きく――
ハタから見れば大袈裟なほどの反応を示していた。
その名前に聞き覚えがあった。聞き覚えがあるなんてものじゃない。ただの知り合いとかでは
なく、彼らに取って物凄く大切な、耳によく馴染んだ名前。
瞬時に持ち前の瞬発力を生かしてさっと拓也が動き、病室の名札を確認する。
先ほどちらっと見ただけではわからなかった。この中に、“あの”名前があっただろうか。
「お……大塚、は――林、かん、崎」
一つ一つ、読みにくい文字を小さな声で読み上げていく。それを瞳と未央は祈るような
気持ちで見守っていた。
どうか。どうか、神様。
ドクン、ドクン、と名前が一つづつ読み上げられると同時に強く心臓が波打つ。
その合い間にも、病室の中ではせわしなく医師たちが動いていて。
「石崎、……それに……」
不意に拓也は声を途切れさせ、ほとんど睨むような視線でその名前をぎっと見た。
「――小松。小松、淳」
しん、と3人の周りを重い静寂が支配した。いっさいの音が、消えてなくなる。
世界がモノクロになり、3人だけが色を持つ存在となる。ゴクン、とつばを飲み込む音
だけが聞こえ、周囲から生物の気配が遠ざかる。
時間的にはほんの一瞬の、そして彼らに取っては永遠とも思えるような時が過ぎると未央は
思い出したかのようにはっと身動ぎ、胸元を強く握り締める。
胸が痛い。心臓がドクドクと脈打ち、今にも飛び出してきそうなほど。このままでは破裂して
しまうのではないかという痛みが、少女の胸を揺さぶる。
「ほんとに……ほんとに、書いてあるの? 読み間違いじゃなく?」
「……ああ……」
「そんな――っ!」
瞳がほとんど悲鳴に近い声を上げると同時に、病室の中から一際大きな声があがる。
絶望的な――そして、彼らが最も聞きたくなかったセリフ。
ピーッという無機質な音が、辺りに響き渡る。
「心拍数、減少! ――停止!」
そのたった一言に、世界がまたも闇に包まれたかのような気がした。
まっすぐに立っていられない。世界そのものが揺れているかのようだ。
「くっ……心臓マッサージを! 強心剤を用意!」
「はい!」
バタバタと動く看護婦の動きを目に映しながら、彼らは目を見開いてただじっとその場に
佇んでいた。
どうしたらいいのか、わからなくなって。
信じたく、なくて。真実を、確認する事もできなくて。
呆然と立ちすくむ中、一番速く我を取り戻したのは瞳だった。
「――淳くん!」
だっと駆け出した瞳を見て、二人もはっと正気に返ってすぐに後を追う。瞳と未央は邪魔な眼鏡を乱暴に毟り取り、帽子を脱ぎ捨てた。そのまま放り投げ、真っ直ぐにベッドへと走り寄る。
痛い。胸が、ココロが、張り裂けそうになる――!
「――淳!」
「ジュン! おい、ジュン!」
「な、あなたたちは――?!」
ベッドに走り寄り、心臓マッサージを施されている少年の下へと3人が駆け寄る。
それを目にした看護婦が驚きの声を上げ、そしてすぐに勤勉な彼女は自分の職務を思い出して
彼らを追い出そうとする。
しかし、それをベッドの横に立っていた若い医師が腕を上げて制する。
ネームプレートには、「浜口」というの名名前。未央を担当した、あの医師だ。
しかし、彼らはそんな周りの事など少しも目に入らなかった。
彼らが目にしていたのは、一人の少年の姿だけだった。
ベッドに力なく横たわり、額に、頬に、腕に、体に、足に、全身いたる所に包帯やガーゼを
はられながら心臓マッサージを受けている、少年。
その髪は、青い銀に輝いていた。美しい髪の色に、その姿は神秘的とも言えるものだったが
それは確かに彼らがよく知る少年の物だった。
彼らの親友。いつも穏やかで、誰よりも頭のいい少年――小松淳。
側に立っていた医師は真っ青な顔をしてマッサージをされている少年を見つめている3人を
見て、すぐに彼らが何者かに気付くと遠慮の無い強い力で取り乱していた未央の肩をつかんだ。
「淳、淳!」
「君! しっかりするんだ!」
「淳、淳!」
「――落ち着くんだ!」
手を伸ばしてイヤイヤと顔を横に振っている少女を抑え、無理矢理押さえつけると彼は決して
大きくはないが力強い声で彼女に呼びかけた。
突然の強い声にびくっと体を震わせ、涙の光る瞳で死にかけている少年を見ていた未央はその声に
初めて反応し、自分の肩を掴んでいる医師を見上げた。
「せん……せい……?」
「君は、彼を知っているのか? 彼の友達なのか?!」
「あ……しん、友で……学校の、同級生……」
隣からギシ、ギシっというベッドの軋む音とピーッと鳴り続ける音、そして拓也達が彼を必死に
なって呼びかける、声。
全てが、遠い幻のようで。
「なら、彼を呼ぶんだ! もっと大きな声で、戻ってこれるように!」
「戻っ……て……?」
怯えた瞳に、微かな光が煌く。若い医師の言葉に彼女がゆっくりと動き出した。
「ああ。君たちが呼べば、彼は戻って来れるかもしれない! 今ならまだ間に合うんだ! ほら、
みんなで一緒に! ――早く!」
頷く暇も無く、背中を押されるがままに彼女はガタガタと振るえながら振り返ってベッドで
マッサージを受けている少年を見やる。
ベッドからはみ出た点滴のチューブの刺さった腕を、瞳がきつく握り締めている。
その隣で拓也が真っ青中で、目に怒りの色を浮かべながら声を張り上げる。
それを目にした未央はさっと自分を取り戻すと、すぐにその隣に行って瞳の手に自らの手を重ねる
ようにして少年の――淳の腕を掴む。
震える手で。冷たくなった彼の手を、きつく。きつく。二人で握り締める。
「……淳。淳、淳、淳!」
「起きろよ、こら! 馬鹿ジュン! 何寝てんだよ!」
「起きてよ淳くん! ねぇ、起きて!」
呼びかけを始めた彼らを横目で見ながら、マッサージをしていた医師は汗を滴らせながら背後に
立つ看護婦に呼びかける。
彼らのためにも、どうか帰ってきて欲しい。
たとえ――それが一時の気休めでも。
「脈拍は!?」
「まだです! 心停止してから、およそ5分!」
「くそ……」
「溝口先生! 交替します!」
息を荒げていた医師に声をかけ、彼を押しのけるようにして浜口医師は淳の上に跨る。そのまま、
両の手で強く胸の中心を――心臓の真上を圧迫する。
常人にすれば、確実に肋骨が折れるだろう力を込めて。それほどまでの力がないと、心臓と
いう器官は再び動こうとはしてくれないのだ。
「淳、淳! 起きなさいよ! この寝ぼすけ!」
「なんでお前は、そう寝汚いんだよ! さっさと起きろ!」
「起きてよ! 起きてったら起きてよ!」
どれほど呼びかけても、何もかわらない。堅く握り締められた冷たい手も、涙に濡れた
熱い視線で見つめられる、その表情にも。
ただ、ピーッという無機質な音が部屋いっぱいに響くだけ。
看護婦達の動き回る音、マッサージを続ける医師の息の音、その動き、それらが必死の声と
混ざり合って響いているだけ。
時は、少しずつ流れ出していて――。
「なんでっ……! 守るって言ったのに!
絶対(って、言ったのに!」
覚えているはずの無い、誓い。
ドン、と強く鈍い音が響く。
拓也が、耐え切れなくなったかのようにパイプベッドの縁に両手を叩きつけたのだ。
未央の見上げたその先に、拓也の顔がある。見慣れたその顔、そのぎらぎらと強い怒りに
輝き煌くその瞳に、涙はない。
「勝手に……俺たちに勝手に、破るな(!
約束を(!」
知るはずの無い、約束。
きつく、きつく握り締めた両の手。まだ大人になりきれていないその中途半端な体は
抑えきれぬ感情に震え、ただ、強い眼差しでのみその苛立ちを現しているかのよう。
瞳と未央は、それを見て少しずつ自分達の中にあった"何か"が動きだのを感じた。
前にも感じた、"何か"。
目覚めたばかりのソレは、強く彼らのうちを焦がし、出口を探そうとそっと動きだす。
彼らの感情のある、どこともわからない場所へと。
――その想いは、同じだから。
「みんなで……生きようって(、
進もうって(、約束したじゃないっ!」
交わしたはずのない、その想い。
ドン、と手を叩きつける音。心臓に響くよう、かなりの力を込めている。密着した状態から
延ばした腕を伝い、その力が胸へと直接押し当てられる。
拓也の怒りに染まった瞳から、いつしかずっと堪えていた涙が静かに零れ落ちていた。
その雫は音を立てずに淳の顔に零れ、動かない表情を伝って流れ落ちる。
「こんなところで死んじゃうなんて、絶対に許さないんだからぁっ!」
どこから出たのかというほど、大きな声が未央の唇からあふれ出す。
きつく閉じた瞼から、際限なく涙が零れるのと同じ様に。
あまりにも突然で。
あまりにも呆気なく。
彼は、死のうとしている。
(死ぬなんて、絶対に嫌だよ……)
(お願いだから、逝かないで……)
(俺たちを残していくなんて……)
「――――淳!」
目を閉ざし、両手を堅く握り締めた3人は全く同じタイミングで、魂から搾り出すかのような
叫び声を上げる。
ふわりと、誰も気付かぬほど微かに、彼らの髪がなびく。風もないのに。
その瞬間。
浜口医師の手の下で、ドクンと、小さな鼓動が響く。
はっきりとそれを感じた彼は、は思わずといったように動きを止めた。
「まさか……」
ばっと彼が振り返ると、その瞬間を待ちわびていたかのようにピーッと鳴り響いていた音が
止み、ゆっくりと……しかし確かなリズムで、ピッピッと音が鳴り出す。
一切の音が消滅した空間で、それだけが存在を主張するかのように鳴り響く。
最初はゆっくりだったものが、次第にペースと取り戻し――やがて、安定した響きを残す
ほどまでなる。
緊張に身を堅くしていた3人は、俯いたまま大きく目を見開いていた。
コノ、オトハ……?
ほぉっと大きな為息をつき、浜口医師は少年の体からゆっくりと降りる。
その表情には、喜びではなく――悲しみが宿っていた。
側に佇んでいた看護婦達にいくつかの指示を出し、見守っていたもう一人の医師に小さく
頷きかけると彼も堅い表情で頷き、静かにその場を去る。
そして、3人と浜口医師、そして眠り続ける少年だけとなる。
彼はゆっくりと歩み、動きを止めて俯き続ける未央の肩をそっと叩いた。
ビク、と肩を揺らして素早く反応して身を起こした未央に、彼は内に秘めた感情を完全に
押し隠した笑顔で声をかける。
「――ありがとう。君たちのお陰だ」
「……え……?」
そろそろ、と顔を上げた拓也と瞳にも笑いかけ、彼は――後ろに隠した右手を強く、堅く握り
締める。気を抜くとすぐにでも溢れ出してしまいそうな激情を抑えるために。
拭いきれない罪悪感と胸を焦がす苛立ちに、彼は微かに震えたと息を洩らす。
大きく息を吸い、そっとその震えを誤魔化すと彼はいっそう嬉しそうな笑顔を浮かべて
見せた。心の中で、ひっそりと謝罪の言葉を呟きながら。
(すまない……)
「……彼は、帰って来れたんだよ……」
静かなその声を聞き、未央と瞳は脱力して床にペタンと尻餅をつく。拓也は身体中を脱力感に
襲われながらもなんとか立ち、胸に溜めていた空気をはぁっと吐き出す。
身体中を包み込んでいた寒気が、ようやっと踵を返したのだ。
「……ったく……いつも、大袈裟なんだよ……」
「……良かった……良かったよぅ……」
「淳……本当に……帰ってきたんだ……」
その目に今度は先ほどとは違う、歓喜の涙を浮かべて彼らは口々に喜びを噛締める。
そんな若者達を見つめながら、彼は一人、静かに踵を返していた。
(今は、まだ……いう必要はないだろう)
パタン、とドアを閉じると、外に一人で待機していてもらった看護婦と目が合った。
人のよさそうな顔立ちの中で、遣る瀬無い哀しみに彩られたその瞳を見て彼は……彼女が
自分と同じ事を感じているのだと言う事を知った。
「……先生……あの……」
「ああ……とりあえず、もう一度ご家族に連絡をするように。それから、彼らはあのままで」
「はい。それで……なんと伝えれば……」
「…………」
ふう、と重いため息が零れる。
言いたくはない。でも、これは自分の仕事なのだ。自分で選んだことなのだ。
人を救うと。そう、心に決めた時にもう一つだけ覚悟した事。
「……ご子息は、もう……。一度心停止を起こされ、恐らく……今夜が峠だと。手の施し様が
ないと。そう、伝えてくれ……頼む」
「……はい」
ゆっくりと歩き出した看護婦を見、彼は深い溜息をついた。
閉じられたドア越しに、彼は小さく呟いた。
「人一人救えないのに、何故僕は医者などと名乗っているのだろうな……」
そうして、彼は歩き出した。